こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- リーダーとは何かを知りたい人
- 管理職に昇進した人
- リーダーを目指している人
※この記事と併せて読みたい記事
内部リンク:仕事でありえないミスを連発→再発防止の仕組み化で価値を生もう
それでは「ヨット講座」始めましょう。
※ヨットはこんな人です。(Twitterのフォロワー数は2020/11/11現在です。)

リーダーとは何か?
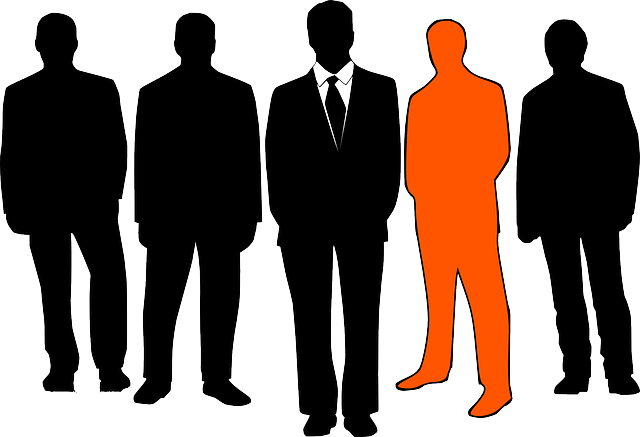
まず、リーダーとは何でしょうか?
総理大臣は総理大臣という役割ですし、社長は社長という役割ですし、部長は部長という役割です。
それ以上でもそれ以下でもありません。
リーダーという役割に求められる力
次にリーダーに求められる役割についてご説明して行きましょう。
「リーダーに求められる役割」と聞くと様々な項目が頭に浮かぶかと思います。
人心掌握、マネジメント力、コーチング力、目標設定力、教養など、様々なことが思い浮かびますよね。
しかし、必須要素ではありません。
こちらの答えも非常にシンプルでたった2つです。
リーダーに求められる力1:決断する力
リーダーに求められる力の1つ目は決断する力です。
これがリーダーの仕事の全てだと言っても過言ではありません。
例えば、国内で大地震が発生したと仮定しましょう。
当然、管轄の国土交通省から様々な判断や対策案が検討され、規模や内容にもよりますが、最終的には総理大臣が決断することになります。
その時に総理大臣が「どうしよう。う〜ん。みんないろいろ言うから決められないなぁ」と言って決断出来なかったらどうでしょう?
対策が何も進まず、国内は大混乱でしょう。
判断を素早くするのはマネージャーの仕事です。
極論すると、リーダーは素早く決断して、責任を背負うことだけが仕事なのです。
リーダーに求められる力2:孤独と向き合う力
リーダーに求められる力の2つ目は孤独と向き合う力です。
基本的にリーダーは孤独です。
なぜなら、最終的には常に自分が全責任を背負って決断することが仕事だからです。
当然、心の内には様々な思いがあるでしょうが、それを吐露できる相手は基本的にいません。
それはなぜでしょうか?
リーダーは組織の代表者です。
様々な思いを自分の中で淡々と処理し、孤独と向き合える人だけが、真のリーダーなのです。
リーダーが心がけたいこと
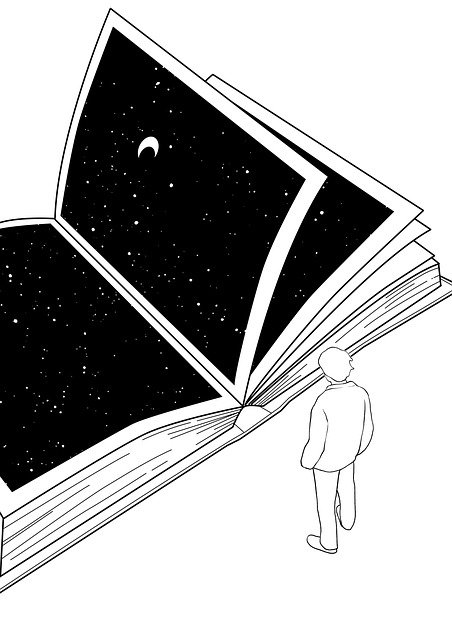
本質的なリーダーの役割は前章でご説明しました。
ここからはリーダーが心がけたい日々の工夫をご説明していこうと思います。
リーダーが心がけたいこと1:日々決断をする訓練をする
リーダーが心がけたいことの1つ目は日々決断をする訓練をすることです。
前章でもご説明しましたが、リーダーは素早く決断をすることが仕事です。
それはなぜかと言えば、日々の訓練を怠っているからです。
日常生活でも訓練できる内容はいくらでもあります。
カフェテリアのランチを3秒で選ぶ練習、服を買いに行った際に5分以内に決める練習など、様々な決断の訓練が可能です。
いざという時に素早く決断が出来ないと、国民、部下などからの信頼を失います。
リーダーのあなた、リーダーを目指すあなたは日々訓練することを意識しましょう。
リーダーが心がけたいこと2:常にワーストケースを考える
リーダーが心がけたいことの2つ目は常にワーストケースを考えることです。
極論を申し上げると、全てが順調に進んでいる時にリーダーは必要ありません。
上手く行っている時には決断が必要ないからです。
決断が必要になるシーンはほぼワーストケースとなったシーンです。
自然災害、製品のリコールなど出来れば発生して欲しくないシーンこそがリーダーの真価を発揮するシーンとなります。
最悪の事態を想像し、対処方法を常日頃からイメージしておく
そのような心構えをしておくと、ワーストケースの時にも落ち着いて対応出来ます。
ワーストケースのシュミレーションで気付いたことをマネージャーに伝え、仕組みを考え直させる。
優秀なリーダーは例外なくそのような仕事の進め方をしているのです。
リーダーが心がけたいこと3:チャレンジを肯定する風土を作る
リーダーが心がけたいことの3つ目はチャレンジを肯定する風土を作ることです。
人材が育つ強い組織の共通点はチャレンジを肯定する風土があることです。
※強い組織の作り方は別の記事で解説していますので、興味のある方はそちらをご一読下さい。
組織というのは非常に興味深いです。
チャレンジを肯定する組織は人材が育ちやすく、正しい仕組みが形成されます。
チャレンジを否定する組織は人材が離職しやすく、腐敗した仕組みが形成されます。
これには一切の例外はありません。
※仕組み化については別の記事で解説していますので、興味のある方はそちらをご一読下さい。
リンク:【仕組み化の方法】自動車メーカーはなぜ強いのかを2つの軸で解説
リーダーの普段の発言を部下は恐ろしいくらいに察知しています。
リーダーが能動的に動くことやチャレンジすることを否定する発言をする組織は必ず問題だらけです。
組織の風土を作るのはリーダーであるあなたなのです。
リーダーが心がけたいこと4:日々の人間観察と人員配置
リーダーが心がけたいことの4つ目は日々の人間観察と人員配置です。
これは私が最も大切だと思っていることの一つです。
私は拘りが強く、不器用なタイプです。(いつもTwitterなどを見てくださっている方は何となくお気づきでしょう。笑)
自動車メーカー時代の組織のリーダーである部長は、私が拘っている部分を日頃から観察した上で評価して下さり、適切なプロジェクトやチャンスを与えて下さりました。今でも感謝しています。
リーダーの人間観察能力や人員配置構想能力は人の運命を変える
私自身、自動車メーカー時代の部長が上司で無ければ、今現在の自分は絶対に無かったと断言出来ます。
日頃から人間観察をし、人の特徴や強み/弱みを把握しておくことです。
また、それを人員配置に反映することです。
強い組織を作り上げるリーダーは必ずと言っていいほど工夫している点です。
リーダーが心がけたいこと5:誰も考えないことを真剣に考える
リーダーが心がけたいことの5つ目は誰も考えないことを真剣に考えることです。
マネージャーが地球のことを考えていると仮定すれば、リーダーは宇宙のことを考えていなくてはなりません。
実例でいくと、事務所のレイアウトなどを真剣に考えていました。
当たり前に染み込んでしまっている部分に改善のヒントがあるのは、仕事、人生の鉄則です。
誰も思いつかないような着眼点を意識することです。
寄り道に思わぬ発見があるのが、仕事や人生の面白い部分なのです。
これからリーダーになる人が心がけたいこと

この記事を読んでおられる方の中には、現在は中間管理職でリーダーを目指している方もおられるでしょう。
そんな方に向けた心得をお伝えしたいと思います。
リーダー候補の心得1:同僚と群れない
リーダー候補の心得1つ目は同僚と群れないことです。
先にもご説明しましたが、リーダーという役割に求められるのは「決断する力」、「孤独と向き合う力」です。
この2つの役割を全うするためには、必須で心得たいのが、同僚と群れないということです。
間違っても飲み会の二次会でワイワイ騒いでいるCチームのレギュラーメンバーにならないことです。
この意味が本当の意味で腹落ちした時、あなたはリーダーになっているでしょう。
リンク:【友達はいらない】友達がいないけれど充実している人の考え方
リーダー候補の心得2:とことん苦しみ抜いておく
リーダー候補の心得2つ目はとことん苦しみ抜いておくことです。
心得1つ目でご説明したように、同僚と群れないと愚痴を言う相手は基本的にいません。
上手くいかない時に愚痴を言えないのは、凄く苦しいことです。
自分がリーダーになると、頻繁に人にアドバイスをする機会が発生します。
その時に深く考えさせられるようなアドバイスが出来るか否かは、あなた自身が苦しみ抜いたか否かなのです。
苦しみ抜くことはリーダーになる人の必須条件です。
これを覚えておきましょう。
リーダーはやりがいだけでやる役割

最後まで読んでくださった方、ありがとうございました。
リーダーはやりがいだけでやるような役割です。あまり旨味はありません。
それでもやりたいと思った人だけが、リーダーになれるのです。
今回は以上です。
※この記事の関連記事は以下です。
リンク:【成長するには?→他責思考を改善しよう!】他責思考改善のヒント
リンク:【会社で出世する人の特徴】出世する人は何が違うのか?
リンク:【部下・後輩指導でお悩みの方必読】指導上手な人は何が違うのか?
リンク:【決断力は人生を豊かにする】決断できない人に贈りたい言葉
リンク:【2030年予想図】今後、仕事で必要とされるスキルとは?
リンク:コストダウンを図るには?自動車メーカーで学んだ5つの思考法
リンク:面白い社内研修は何が違うのか?社内研修を充実させる小さな工夫
リンク:【会議の進め方】短い時間で効果を発揮する会議は何が違うのか?
リンク:【整理整頓力】家庭、仕事で能力を発揮する人の6つの考え方
リンク:【評価上昇確実】今日から使えるビジネスメール術 4選
