こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人のために書きました。
- 読書ができない、苦手だと感じている人
- 本の読み方のコツを知りたい人
- 読書のメリットを知りたい人
※この記事と併せて読みたい記事
内部リンク:【人生が変わる】20代で必ず身につけたい習慣 8選
内部リンク:【本の楽しみ方】人生を変えるおすすめの本の楽しみ方 5選
内部リンク:【小説の楽しみ方】人生を変える小説の楽しみ方 5選
内部リンク:効果大:読書ノートの書き方はここで差がつく!人生の相棒の作り方
内部リンク:【本の目利き・選び方のコツ】アタリ確率を上げるには○○を確認
※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/1/5現在です。)

読書ができない、苦手な方におすすめしたい方針

先日、下記のTweetをしました。
読書ができない、苦手だという方は自分の中のハードルをあげてしまう真面目な方が意外に多いです。
あまり身構えなくても大丈夫です。
毎日1ページ、2ページでも継続すると大きな力になります。
この記事は読書ができない・苦手な方、読書術について知りたい方、本の読み方のコツを知りたい方、全ての方に読んで頂きたい内容です。
読書を通じて得た実績
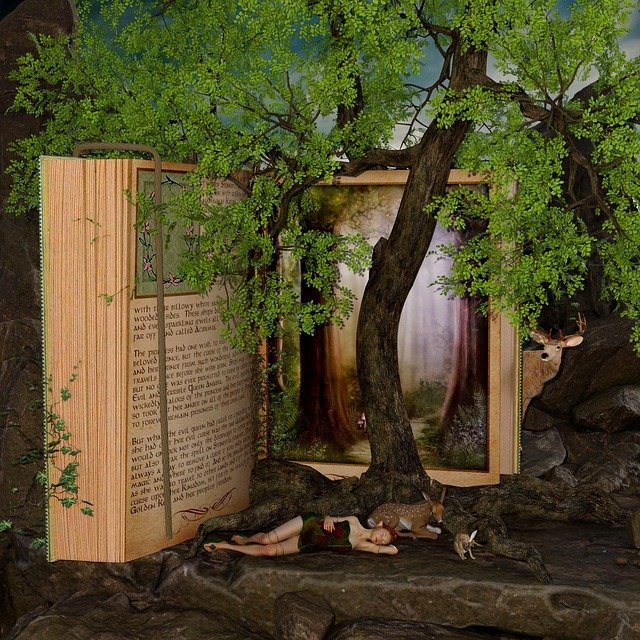
まずは私の簡単なプロフィールをご説明したいと思います。
多少なりとも読書について語るような実績があるのか?を読者の方は問いたいところだと思いますので。
読書の歴史
本格的な読書は高校生からスタート。現在30代前半です。
これまでの読書量は少なくとも500冊以上。
500冊以上と書いたのは、今手元にある蔵書が500冊ピッタリだからです。
500冊を超える時は必ず何かを1冊手放すようにしています。
要はいちいち何冊読んだか?みたいなことを数えていません。
少なくとも1,000冊以上は読んでいるはずですが、正確に数えたことが無いのでわかりません。笑
正直なところ、趣味に近いです。
読書のジャンルも哲学書、小説、自己啓発、ビジネスと様々です。
おすすめの本については別の記事にまとめていますので、興味のある方は下記のリンクからご確認下さい。
職歴
(転職活動ではその他職種の従業員数1万人以上某大企業からも高く評価して頂き、内定を頂いた実績があります。)
Twitterではよく呟いている内容なのですが、海外3ヵ国でのプロジェクト立ち上げ、大規模工場再構築プロジェクトなどに主要メンバーとして従事し、数々の経験・体験を積み重ねて来ました。
現在は紹介制経営コンサルで細々とご飯を食べています。
年商〇〇億や起業家、カリスマブロガーと言ったような華々しさはありませんが、大した学歴/頭脳の無い凡人にしては、まぁまぁのキャリアでは無いでしょうか?
私が自信を持って言えることは、このようなキャリアを積んで来られたのは、確実に読書から享受したメリットのおかげです。
自分の才能を客観的に見つめれば見つめるほど、いかに読書が大きなメリットを持っているかよく分かります。(笑)
読書は人生を大きく変える可能性がある

読書は人生を大きく変える可能性を秘めていると考えています。
この記事を見て頂きたい方は「凡人」の方です。(言い方が失礼だったら申し訳ございません。)
正直なところ「天才」や「超高学歴エリート」の方は何をやっても成功する確率が非常に高いです。
「天才」や「超高学歴エリート」の方はこの記事を読んでいる暇があったら、自分の好きなことをやって下さい。その方が成功する確率が高いです。笑
典型的な「凡人」であり、「駄馬」である私がいかにして、それなりのキャリアを積み、「速く走れる」ようになったのか?
今日は私の読書術、本の読み方のコツをご紹介いたします。
本の読み方のコツ 6選
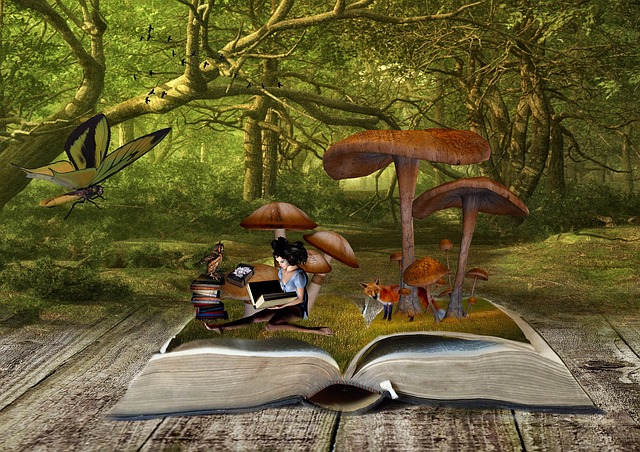
読書が趣味の私が語り始めたら、1週間では足りなくなってしまうので(笑)、重要だと思っている部分を6つピックアップし、本の読み方のコツとしてご紹介させて頂きます。
- 目的を明確に!「キーワード」or「化学反応」
- アウトプットの質:「何冊」より「化学反応発生数」
- 思考法:「模範解答」より「生き様との混合」
- 重要なこと:感じ取る力を磨く
- 贔屓の著者を3人探そう!
- 贔屓の著者の本を徹底的に読み込もう!
それでは前置きが長くなりましたが、解説を始めましょう。
本の読み方のコツ1:読書の目的を明確に!
正直に申し上げると、私は読書が趣味なので、「目的なんか要らない」と思っているタチですが(笑)、人生を振り返ってみると無意識ではありますが、目的を明確にして読書をしていたように感じます。
キーワードを拾う読書
「キーワードを拾う」というのは、新しい視点を手に入れるということです。
例えば、あなたの時間が足りないとしましょう。
そのような場合の一例ですが、時間術の本を購入して、ざざっとと読むことでしょう。
そこで「速く歩く」や「ショートカットキーの活用」といった新しい視点を入手することが「キーワードを拾う」ということです。
「速く歩く」や「ショートカットキーの活用」には特に深い思考は必要ありません。
化学反応を起こす読書
「化学反応を起こす」というのは読書を通じて、著者の主張と格闘し、自分の中で変化を起こすということです。
古今東西の天才哲学者達の著書を読むと、これは非常に分かりやすいです。
私が好きな哲学者ジャン・ボードリヤール氏の本で例えて考えてみましょう。
ボードリヤール氏の各著作を徹底的に読み込んでいくと分かるのですが、哲学者のバタイユ氏、フーコー氏、作家のルイス・ボルヘス氏などから色濃く影響を受けていることが分かります。
まず、第一ステップとして、偉人達の著作を一言一句、徹底的に読み込んだ上でその思考プロセス、主張を自分なりに解釈します。これが著者の主張と格闘するということです。
次に第二ステップとして、納得できた部分は自分なりの言葉で語れるようにノートなどに自分の言葉で書き留める、納得できない部分は反証的、逆説的に考えて自分の主張をノートに書き留める。これが自分の中で変化を起こすということです。
凡人の私がいろいろと試した結果、熟読が最適でした。
(私の熟読を速読のスピードでこなしてしまう天才も世の中にはいます。自分の頭脳レベルを客観的に見ながらいろいろ試しましょう。)
読書の目的は使い分けよう!
この二つのステップで自分の中に化学反応を起こしていく訳です。
どちらを目的にするのか?を意識して読書に臨むことでインプットの質がまるで変わってきます。
ご説明した内容で是非、自分なりに試行錯誤してみて下さい。
本の読み方のコツ2:アウトプットの質を意識する
少し批判的な意見になってしまうのですが、「年間〇〇冊、読破」みたいにアピールする人がいますが、端から見ると「・・・で?」という感じです。
1:1,000冊の読書をし、100個の「キーワード」をアウトプットできる人
2:100冊の読書をし、500個を「自分の言葉」にしてアウトプットできる人
どちらが実社会で役に立つでしょうか?
私は後者だと思っています。
「手段」が「目的」になってしまっては本末転倒です。
これは「努力家」の方が陥りやすい罠なので注意しましょう。
※正しい努力についての考え方については別の記事にまとめていますので、興味のある方はご一読下さい。
本の読み方のコツ3:「模範解答」より「生き様との混合」を意識する
読書をした後のアウトプットで大切な思考法があります。
それは「模範解答」より「生き様との混合」ということです。
「生き様」は私がTwitterで多様するキーワードの一つです。笑
インターネットや検索エンジンの発達により、「模範解答」は一瞬で検索できる時代です。
現代社会では一瞬で検索し、分かることの価値は非常に低くなっています。
大切なことは「模範解答」をマスターしつつ、自分の人生体験と組み合わせて「生き様」として語ることです。
人が深く惹かれる言葉というのはその人の「生き様」が滲み出た言葉なのではないでしょうか。
本の読み方のコツ4:読書以前に重要なこと→感じ取る力を磨く
本の読み方のコツ、読書以前に意外に大切なことがあります。
それが「感じ取る力」です。
これは意外に見落としがちな盲点です。
極端な話、同じ本を読んでも、人によって全く吸収度が異なります。
その差がどこから来るのかと言えば「日常の体験」です。
読書の効果を最大限に発揮するためにも、日常の様々なことに感想を持つ癖をつけたり、能動的に行動することが大切です。
私の場合は病気で大きな手術をしたことで、「感じ取る力」が急激に上がりました。
どんな経験でも後々になって、「良かったな」と思える出来事に変化するのが、人生の面白いところですね。
本の読み方のコツ5:贔屓の著者を3人探そう!
様々な本を読んでいくうちに、「この語彙力は凄い」「この視点は凄い」「世界観に引き込まれる」著者に出会うと思います。
そのような著者を、「哲学」、「小説」、「自己啓発」のそれぞれの分野で1人ずつ見つけておくと良いです。
不思議とその状況を「打開するヒント」を授けてくれるのです。
自分が「世界観に引き込まれる」著者を探すのも、読書の楽しみ方の一つだと思っています。
本の読み方のコツ6:贔屓の著者の本を徹底的に読み込もう!
幸運にも「世界観に引き込まれる」著者に出会ったら、その著者の本を少なくとも最低10冊以上は読み込んでおくことをお薦めします。
何か課題が発生した時や、壁にぶつかった時にも、「〇〇氏ならどう考えるだろう?」と考えると、大抵ヒントになる内容が発見できるようになります。
本の読み方のコツは1人の贔屓の著者を1点突破してから横に広げる、いわゆる「T字型戦略」です。
「思考の土台」ができてから、他の本を読むと、今まで以上に多角的に物事を捉えられるようになりますしね。
この本の読み方のコツを実行すると、深く読書を楽しめるようになります。
読書は人生を豊かにする
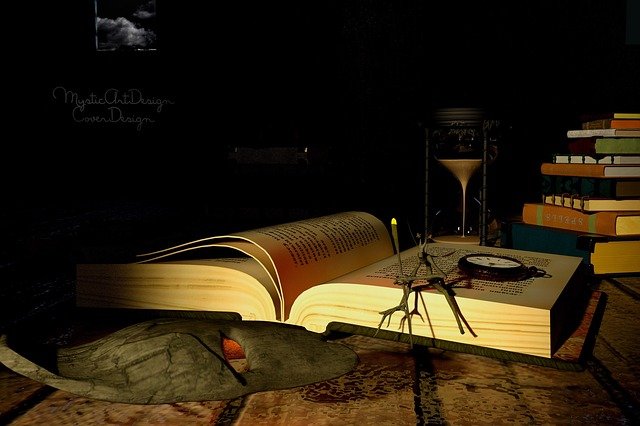
最後まで読んでくださった皆様、ありがとうございました。
最後にこんなことを申し上げるのは恐縮なのですが、本の読み方のコツや読書に「模範解答」はありません。
自分の人生を有意義に過ごすためのツールが読書です。
今回、作成した記事があなたの「生き様」の要素に少しでも加われれば幸いです。
今回は以上です。
