こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- 仕事でありえないミスを連発して落ち込んでいる人
- 部下・後輩が仕事でありえないミスを連発して悩んでいる人
- 仕事でありえないミスが連発した時に考えるべきことを知りたい人
※この記事と併せて読みたい記事
内部リンク:仕事の大失敗で立ち直れない人→使命:経験を未来の部下に伝える
内部リンク:【仕事の忘れ防止:対策方法6選】仕事を忘れない小さな工夫
内部リンク:【0から1を生み出す人が仕事のできる人】0から1をつくる方法
内部リンク:仕事についていけないと思った時→3つのポイントを再確認しよう
内部リンク:仕事で雑用ばかりという人へ→まずは雑用を完璧に仕上げること
それでは「ヨット講座」始めましょう。
※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/4/5現在です。)

仕事でありえないミスを連発→成長するチャンス

この記事を読んで下さっている方には様々な方がいらっしゃるかと存じます。
「自らが仕事でありえないミスを連発してしまった・・・」という方。
「部下・後輩が仕事でありえないミスを連発した」という方。
はたまた「取引先が仕事でありえないミスを連発した」という方。
「どこがチャンスなんだ!」とお怒りの声が聞こえてきそうですので、解説させて下さい。(笑)
「仕事でのありえないミスの連発」→自責思考で考える
先述したいずれかのケースで「仕事でのありえないミスの連発」に遭遇した場合、非常に大切なポイントがあります。
それは他責思考ではなく、自責思考で考えることです。
内部リンク:【他責思考を改善する/させるには?】他責思考改善のヒント
自らが仕事でありえないミスを連発してしまったならば、外的要因を探すのではなく、内的要因を徹底的に探すことです。
部下・後輩が仕事でありえないミスを連発したならば、自分の仕事の任せ方や指示、組織の仕組みなどを見直してみることです。
取引先が仕事でありえないミスを連発したならば、自分の仕事の任せ方や指示、依頼のタイミングや仕組みなどを見直してみることです。
外的要因を探したり、「ありえない」と一蹴するのは小学生でもできます。
しかし、内的要因を探したり、自分の関わり方を真剣に考えると、今まで見えなかったものが見えるようになるのです。
「仕事でのありえないミスの連発」→仕組みを見直すチャンス
「仕事でのありえないミスの連発」は発生した瞬間から「ありえる」ことなのです。
ここで「ミスをした人」にフォーカスを当てる企業・組織・上司は三流です。
一流の企業・組織・上司は「ミスが発生した仕組み」にフォーカスを当てます。
内部リンク:一流、二流、三流の違い→普段の思考/考え方に違いが顕在化する
トヨタ自動車が発祥とされる有名な言葉に「人を責めるな、仕組みを責めろ」という言葉があります。
仕事でのありえないミスの連発が発生した時は仕組みを見直すチャンスなのです。
仕事でありえないミスを連発した際の考え方【個人編】

ここからは、「仕事でありえないミスを連発した際の考え方【個人編】」を解説していきます。
あなたがミスを連発したつもりで当事者意識を持って考えてみましょう。
内部リンク:【当事者意識を持つと仕事での成長が早い】当事者意識を持つ/持たせるには?
仕事でありえないミスを連発した際の考え方【個人編】1:暫定・恒久・再発防止を考える
仕事でありえないミスを連発した際の考え方【個人編】1つ目は暫定・恒久・再発防止を考えることです。
- 上司に報告する
- 暫定対応を考える
- お客様・関係者などに連絡し、謝罪する
- 恒久対策を考える
- 再発防止を仕組み化する
仕事でありえないミスを連発した場合ほど、これらの事後処置をスピーディに行うことが大切です。
またその後は腰を据えて、下記の対策を実施する必要があります。
- 暫定対策→お客様・関係者にご迷惑がかからないようにする一時的な処置
- 恒久対策→問題点を根本から取り除く恒久的な処置
- 再発防止→ありえないミスを再発させないための内容を仕組み化
仕事でありえないミスを連発した際の考え方【個人編】2:予習・準備過程を振り返る
仕事でありえないミスを連発した際の考え方【個人編】2つ目は予習・準備過程を振り返ることです。
予習・準備を入念にしている人は問題が早い段階で顕在化します。
いくつか例を挙げましょう。
「あれ、このデータ間違っていないか?」、「原価回収の計算式が間違っていた」などの重要な前提条件の誤りを予習・準備段階で発見し、命拾いする例は枚挙に暇がありません。
逆に予習・準備を疎かにしている人はどうでしょうか?
「原価回収の計算式が間違っていた」→「うわ、桁が一桁間違っている。大赤字だ・・・」となることでしょう。
あなたはどのくらい予習・準備に力を入れているでしょうか?
自信が無かった方は下記の記事をご一読下さい。
内部リンク:【仕事は予習・準備で8割以上が決まる!】予習・準備のコツ5選
仕事でありえないミスを連発した際の考え方【上司・先輩編】
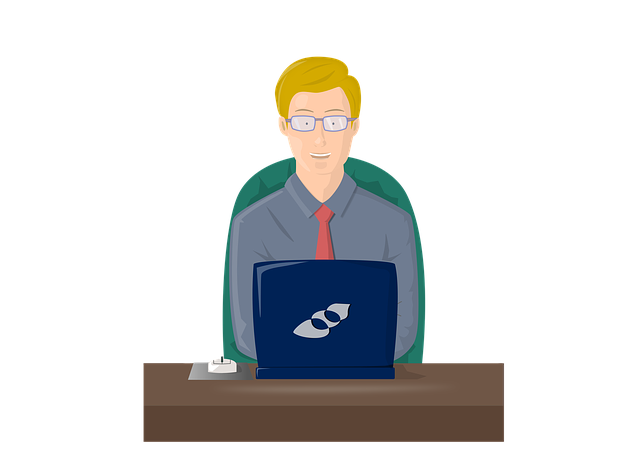
ここからは「仕事でありえないミスを連発した際の考え方【上司・先輩編】」を解説していきます。
部下や後輩が仕事でありえないミスを連発したと仮定して考えてみましょう。
仕事でありえないミスを連発した際の考え方【上司・先輩編】1:責任を取る
仕事でありえないミスを連発した際の考え方【上司・先輩編】1つ目は責任を取ることです。
リーダーや管理職の仕事というのは究極2つしかありません。
「決断すること」「責任を取ること」の2つです。
なぜなら、部下を管理する責任を負っているのはあなたなのですから。
だからこそ、お給料が部下よりも高く、権限があるのです。
上司であるあなたがこの姿勢を見せると、仮にあなたの部下が将来的に出世して、同じシーンになった時には「責任を取る」上司になることでしょう。
人間というのは自分がして貰ったことを将来リピートする生き物なのです。
内部リンク:【リーダーとは何か?】現代社会のリーダーに求められるもの
仕事でありえないミスを連発した際の考え方【上司・先輩編】2:部下の適性を考慮する
仕事でありえないミスを連発した際の考え方【上司・先輩編】2つ目は部下の適性を考慮することです。
人間というのは向き/不向きがあります。
マラソンが得意な人に相撲をさせても上手くいきません。
魚を陸に揚げたら泳げません。
上記は誰がどう考えても上手くいかないことが理解できます。
しかし、我々は仕事になると「仕事だから」の一言で片付けてしまいがちです。
上司の仕事は部下の能力を最大限まで引き出してチーム・組織としての成果を発揮することです。
サッカーの世界などでもポジションをコンバートすることで才能が開花することは珍しくありません。
人を活かす仕組みを考えるのも上司の仕事なのです。
仕事でありえないミスを連発した際の考え方【上司・先輩編】3:組織的な再発防止の仕組み化
仕事でありえないミスを連発した際の考え方【上司・先輩編】3つ目は組織的な再発防止の仕組み化です。
ありえないミスの再発を防止するための仕組みを整理し、マニュアル化することです。
リーダー・管理職が考えるべきことは「誰がやっても」「高い再現性」を出せる組織をいかに作るかということです。
そんな観点で考える発想が必要なのです。
内部リンク:【ビジネスでの仕組み化の方法、作り方】自動車メーカーを2軸で解説
内部リンク:【強い組織の特徴 6選】自動車メーカーで学んだ強い組織の作り方
今回は以上です。
