こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- 新入社員で会議の進め方が分からない人
- 会議が苦手、会議がうまくいかない人
- 長い会議を効率化して、短くしたい人
- 会社の会議の進め方に疑問がある人
※この記事と併せて読みたい記事
内部リンク:仕事が進まない時→着地点から逆算して、なぜ進まないかを考える
内部リンク:仕事でのキャパオーバー→自分が成長するチャンス【新人必読】
内部リンク:【2030年予想図】今後、仕事で必要とされるスキルとは?
内部リンク:【人生・仕事で大切なこと→要点をおさえる】要点をまとめる方法
内部リンク:【0から1を生み出す人が仕事のできる人】0から1をつくる方法
内部リンク:守備範囲が広い人は仕事ができる、ビジネスで成果を出す守備範囲
それでは「ヨット講座」始めましょう。
※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterのフォロワー数は2021/1/11現在です。)

会議の進め方は生産性/成果に直結する

私は従業員1万人弱の自動車関連企業と自動車メーカーの2社でサラリーマン経験をして来ました。
具体的な年数を申し上げるとおっさんなのがばれますので(笑)、詳細は控えますが10年以上、サラリーマン生活を送って来ました。
大企業は会議が非常に多いです。
特に自動車メーカーの場合、関係部署も非常に多いですし、調整のための会議が日常的に必要になります。
厳密には数えたことが無いので分かりませんが、どう少なく計算しても3000回以上の会議に参加して来ました。
自分で会議を開催したり、開催された会議に参加していて気付いたことがあります。
更に詳細を観察していくと面白いことに気づかされました。
それは短く、効率化されているにも関わらず、いくつもの合意事項や調整事項が決まる会議を開催する人物はいつも同一人物だということです。
逆もしかりでした。いつも長いのに何も合意が得られず、何も決まらない会議を開催する人物もいつも同一人物でした。
もちろん生産性や成果に直結していることは申し上げるまでも無いでしょう。
興味を持って、いつも短く効率化された会議の進め方をする何人かを観察すると、共通点を発見しました。
今日はその短く効率化された会議の進め方、「型」をお伝えして行きたいと思います。
会議の目的とは?
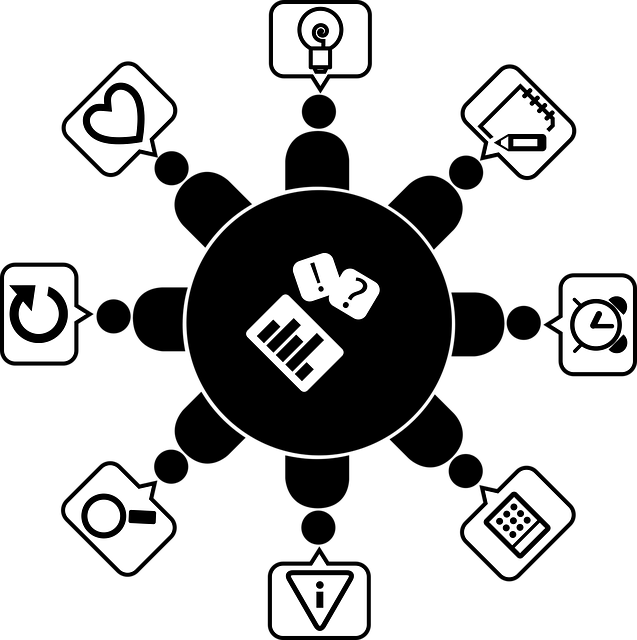
具体的な会議の進め方を説明していく前に、会議の目的について考えましょう。
これは自動車メーカー時代に周囲を観察した結果、100%、一つの例外も無い一次情報です。
会議の目的:3つの要点
- 内容の調整を行い、合意を得る
- 日程軸の合意を得る
- 役割分担を振り分け、アクションを決める
押さえるべき目的はこの3点です。
それ以上でもそれ以下でもありません。
この3点を押さえるために話をする人と漠然と話を進める人とでは天と地の差がついてしまいます。
この内容は手帳にメモして、会議開催前に必ず5秒で良いので確認しましょう。
私はそうしていました。
会議を開催する前に「無駄な会議」ではないかを自分に問う
会議を開催する前に重要な視点があります。
自動車メーカー時代の一次情報ですが、何を調整したいのか全く分からない会議をスケジューラーに放り込んでくる輩が必ず複数名います。(笑)
取引先にも、何が話したいかが明確になっていないのにも関わらず、「打ち合わせをお願いします」と申し出てくるメーカーが複数社ありました。
私はそのような人々には徹底的に質問をするようにしていました。
「メールでのやり取りで決まる内容ですし、エビデンスも残るので、メールではダメですか?」
「具体的に貴社として、何を課題だと思っており、何を調整したいかをエクセルにまとめて頂きご教示下さい。その内容を拝見させて頂き、会議の必要性を判断します。必要性を感じなければ、頂いたエクセルに回答を記載して指示します。」
そもそも会議と言うのは、メールのやり取りだと効率が悪い内容や緊急課題の方向性を決定するような内容以外は不要だと考えています。
何が決めたいかよく分からない会議に、言われるがままに出席していたら、体がいくつあっても足りません。
と言うことは自分が開催しようと思っている会議も「無くせないか?無駄ではないか?」と必ず自らに問う必要があります。
「何となく」開催する会議は全て無駄です。
会議は重要ですが、会議を無くす/減らす仕組みを考えることは更に重要です。
少し論旨から外れるかもしれませんが、非常に重要な視点なので、これを読んで勉強している優秀なあなたは是非覚えておきましょう。
会議の進め方:5つのポイント

- 会議は事前準備が全て
- 会議は最小人数で行う
- 会議は開始時がキモ
- 会議は抽象度を上げて、合意の接点を見つける
- 会議では議事録を必ず取る
会議の進め方1:会議は事前準備が全て
会議の進め方1つ目は会議は事前準備が全てだということです。
要は会議前にほぼ、結末は決まっています。
いつも会議が上手く進まない人は会議前の準備を疎かにし、会議で永遠と議論に終始し、「また来週、資料を準備して打ち合わせをさせて下さい」となっています。
何やら笑い話のようですが、100%ノンフィクションの一次情報です。
大切なことはあなたが後者にならないことです。
では具体的に何を準備したら良いのでしょうか?
更に深堀りして解説して行きましょう。
会議前に準備・段取りするもの
会議前に準備・段取りする3つの要点について考えて行きましょう。
- ①会議目的
- ②構想日程表
- ③その他必要資料
①会議目的
具体的には以下の2点を自分に問いましょう。
- 何が決めたいのか?
- 何が論点・争点なのか?
例えばですが、クリスマス用のチキンを仕入れる数量を決めたいのか、仕入れる産地を決めたいのかで全く準備する資料が異なってきますよね。
会議の進め方が下手で何も決まらない人の会議依頼タイトルは「クリスマス用チキンについて」です。
これでは会議で何が決めたいのか全く分かりません。
何が決めたいのかをきちんと会議前に言語化しましょう。
例えばクリスマス用チキンを例年の倍の1000羽仕入れたいとします。
1000羽の仕入れは確定だと仮定した場合の論点は「冷凍保管スペースの確保可否とオペレーション方法」「1000羽を調理するための人員体制の構築」「売り場面積の確保」などが考えられます。
大切なことはこの論点・争点を会議前に自分で考えることです。この論点・争点が自分の中で想像出来ていると、事前に下調べが出来ます。
上記の例ならば、冷凍保管スペースの空き状況を自分で見に行ったり、売り場のスペースサイズを測定したり、現場の責任者と下話をして相談しておくなどが考えられます。
このように事前に論点・争点の足場を固め、自分の考えを持って打ち合わせに臨むか否かで会議結果に差が付くのは申し上げるまでもありません。
②構想日程表
会議を進める上で押さえたいポイントは日程軸です。
いつ、どこで、誰が、どのように動くかを決めるためには必ず、日程案がなくてはなりません。
貴重な時間を無駄にしないためにも、構想日程表は必ず作成し、持参するようにしましょう。
内部リンク:【自動車メーカーの日程表の書き方】日程表で押さえるべきポイント3つ
内部リンク:【日程・スケジュール管理のコツ】管理できない人が心がけるべきポイント7選
③その他必要資料
自分はどのように考えて、どのあたりに着地するのかを想像しながら、会議に必要な資料を準備することが大切です。
これは会議に参加するキーマンの考え方の癖でかなり準備するものが変わりますので、キーマンの思考回路をよく観察するようにして下さい。
会議案内メールは非常に重要
会議前の段取り・準備と並行して、会議の案内メールを送りましょう。
内部リンク:【メールタイトル・書き方はセンスの集大成】ビジネスメール術 4選
終了時刻を指定し、後が埋まっている会議室を取るようにしましょう。
これが意外にも短く効率化した会議を開催するコツです。
すごーく地味なのですが、意外に効きます。
会議の進め方2:会議は最小人数で行う
会議の進め方2つ目は会議は最小人数で行うことです。
これを読んでいるあなたは真面目で優秀な方でしょう。
当然、将来出世して経営陣の仲間入りを果たしている可能性も大いにあります。
実務担当者レベルだと、「呼んだからね」みたいな感じで、やたらと人を参集してしまいがちです。
これは経営視点から見ると、大バツです。
会議で発言しない人、一言も喋らないような人を呼ぶ必要性は一切ありません。
お金をドブに捨てているようなものだからです。
「絶対に必要な人を最小人数呼ぶ」、これが会議の鉄則です。
将来の出世頭であるあなたには是非覚えておいて頂きたい視点です。
キーマンを見極め、必ず参集する
会議は最小人数で行うのが鉄則です。
大体、どこの会社にも「この案件なら〇〇さんだな」みたいな優秀かつ周りを統率するパワーを持った人物がいるはずです。
たった今、これを書いている私の頭の中にも、サラリーマン時代にお世話になった方が何名か思い浮かんでいます。(笑)
そのような人が誰かをきちんと見極め、絶対に参集することです。
場合によっては、その人が出られないなら、会議を延期する選択肢もあるくらいに重要なことです。
会議の進め方3:会議は開始時がキモ
会議の進め方3つ目は会議は開始時がキモだということです。
会議を失敗する進め方のパターンがあります。
それは会議のゴールが定まっておらず、話があちこちに飛び火して、収集が付かなくなるパターンです。
どこの会社にもよく分からない方向に話を持っていく「おっさん社員」が1人はいるものです。(笑)
PS.終了時刻も開始直後に宣言するようにしましょう。
短く効率化した会議にするために「終了時刻」のアンカリングも欠かせません。
会議の進め方4:会議は抽象度を上げて、合意の接点を見つける
会議の進め方4つ目は会議は抽象度を上げて、合意の接点を見つけることを意識して下さい。
会議をしていると、主張が異なり、合意出来ない場面というのは少なからずあります。
そこで大切になるのが、抽象度を上げて、合意の接点を見つけるという発想です。
何も合意出来ずに終わってしまうパターンというのは、抽象度が低い部分で主張が食い違い、平行線をたどるパターンです。
頷いてしまった方も多いのでは無いでしょうか?(かつての私の失敗そのものなので、何やら懐かしいです。笑)
会議で合意の接点を見出すケーススタディ
例えば、あなたが会社の美化委員で清掃活動を促進する責任者だとしましょう。
週1回、1時間、全部署参加の清掃活動を企画したが、各部署からの大反対に遭っているとします。
ここで大切なことは一度抽象度を上げて会話してみることです。
例えば「会社及び会社の周囲を清掃することは会社のイメージUPや地域貢献、地域密着の観点から非常に重要だと考えています。その点についてはいかがでしょうか?」と会議参加者に問うてみます。
この問いに対しては、全部署から合意が得られました。
合意の接点が見つかった段階で、再び抽象度を徐々に下げて行きます。
例えば「地域貢献、地域密着の観点での重要性についてはご理解頂きました。皆さんが週1回、1時間、全部署参加の清掃活動に反対する理由をご教示頂けないでしょうか?」と再び問うてみます。
そうすると、各部署の責任者からは「全部署、週1回、1時間清掃は業務負荷とのバランス的に苦しい」という声が挙がります。
そこで「分かりました。各部署持ち回り制に変更し、清掃活動は30分であればいかがでしょうか?各部署の割り当てが2ヶ月に1回になるので、これなら、バランス的に悪く無いのではないでしょうか。」
これで各部署の責任者が納得すれば、合意完了です。
この考え方は実践的でかなり使えますので、試してみて下さい。(私は実際の会議でも、階層別研修などでも多用していました。)
会議の進め方5:会議では議事録を必ず取る
会議の進め方5つ目は会議では議事録を必ず取ることです。
これには一つの例外もありません。
一番始めにも申し上げましたが、会議の目的は以下の3点です。
- 内容の調整を行い、合意を得る
- 日程軸の合意を得る
- 役割分担を振り分け、アクションを決める
この3点の要点を押さえ、議事録に落とし込むことが重要です。
要は共通指針を言語化して、共有することが大切です。
議事録の取り方については以下の記事にまとめてありますので、リンクを貼っておきます。
会議を制すものは業務を制す

最後まで読んでくださった方、ありがとうございました。
優秀なあなたは当たり前のようにやっていることかもしれませんが、この記事に書いてある内容を是非試してみて頂ければと思います。
一つでも参考になった項目があれば嬉しいです。
今回は以上です。
