こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- 議事録が苦手な人/書けない人
- 議事録の書き方/まとめ方のコツ/ポイントを知りたい人
- 会社の議事録の書き方に疑問がある人
※この記事と併せて読みたい記事
内部リンク:仕事が進まない時→着地点から逆算して、なぜ進まないかを考える
内部リンク:【人生・仕事で大切なこと→要点をおさえる】要点をまとめる方法
内部リンク:【仕様書の書き方 10のポイント】自動車メーカーの仕様書を徹底解説
それでは「ヨット講座」始めましょう。
※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/1/9現在です。)

はじめに:議事録を書く目的とは?

はじめに、議事録を書く目的とは何でしょうか?
書く目的を理解して議事録を書いている人と、そうでない人とでは議事録の質に雲泥の差が出てきます。
実はここが議事録が得意な人と苦手な人、書けない人の一番大きな差かもしれません。
議事録の書き方/まとめ方のポイント/コツについて解説する前に、まずは書く目的を正しく理解するところから始めさせて下さい。
- アクションの明確化
- 認識相違の防止
- 長期スパンでのPDCAへの活用(決定プロセス等の履歴を長期スパンでも振り返れるようにする。)
順番にご説明して行きましょう。
議事録を書く目的1:アクションの明確化
議事録を書く目的の1つ目はアクションの明確化です。
これは次章以降で詳細をご説明しますが、何が合意出来て、何が課題で、どんな日程軸で、誰が何を担当するのか。
一人で仕事をしているフリーランスであれば、原則、議事録は不要です。(当然、対お客様との議事録は必要です。)
しかし、自動車メーカーのような大きな組織で動く際には、議事録を書き、役割分担を割り振らないと、それぞれのアクションがあやふやになってしまいます。
そこで非常に大切になるのが、議事録でそれぞれのアクションを明確にするということになります。
全員の共通指針を明確にし、アクションを起こす(起こさせる)一つのツールが議事録という訳です。
議事録を書く目的2:認識相違の防止
議事録を書く目的の2つ目は認識相違の防止です。
仕事でよくあるパターンはお互いの認識が食い違っているまま、進んでしまい、最後に顕在化して爆発するパターンです。(笑)
議事録というのは、必ず文字情報に言語化する必要があります。
このプロセスが非常に重要です。
認識の相違というのは必ず曖昧な部分から生まれます。
議事録を書くという行為により、言語化し、認識相違を無くしていくことが非常に重要になります。
全てがリアルタイム化し、高速化した社会では時間の余裕がありませんので、尚更です。
議事録を書く目的3:長期スパンでのPDCAへの活用
議事録を書く目的の3つ目は長期スパンでのPDCAへの活用です。
実は私が一番重要だと思っている部分はこの内容です。
議事録の良いところは記録として残ることです。
PDFや電子データファイルに連番を付与して、採番台帳システムで管理すれば、必要な時に、必要な情報をおさらいすることが出来ます。
人材の流動性が高まっている現代社会では、担当者の人事異動や、転職、独立などは珍しいことではありません。
そのような社会情勢の中では、決定プロセス等の履歴を振り返れるように議事録を作成し、管理することが非常に重要です。
例えば、プロジェクト完了から1年経った段階で、定量的な効果測定を実施した結果、思わしく無い指標が出た項目があったとしましょう。
その時に大切になるのは、過去の議事録を振り返り、どの部分の前提条件定義や方針に誤りがあったのかを認識することです。
しかし、議事録が無いと決定プロセスが不明確かつ曖昧なものとなり、正しい振り返りが出来ません。
強い組織や個人に共通することは、何らかの形で記録に残し、上手くいった時も上手くいかなかった時も必ず振り返りをする癖があるのです。
議事録はそのための優秀なツールなのです。
議事録の書き方/まとめ方:7つのポイントとコツ
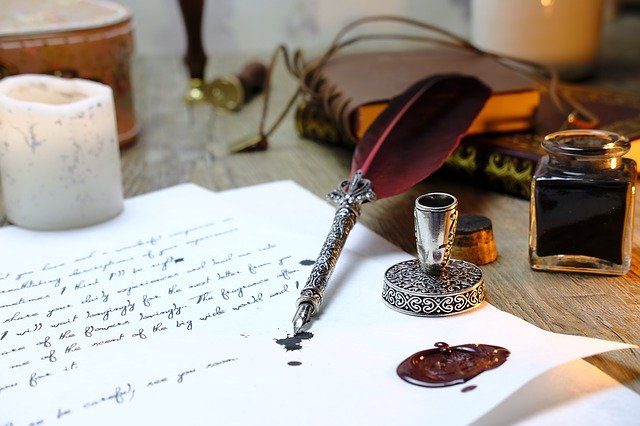
ここからは具体的な議事録の書き方/まとめ方について、具体的な事例を出しながら、ポイント/コツの解説を進めて行きます。
このポイント/コツに沿って書けば、どの会社でも基本的にまず大丈夫と考えています。
議事録の書き方/まとめ方で押さえるべきポイント
それが以下の7つのポイントです。(会社や上司などによって求める内容が異なると思いますので、必要に応じて増減して下さい。)
- 打ち合わせ件名
- 打ち合わせ日時・時間・場所・参集者
- 打ち合わせ目的
- 日程軸
- 結論
- 質疑応答抜粋
- 残課題及び今後の進め方
何故、この7つのポイントが大切になるのか?を項目毎にご説明して行きます。
議事録のポイント1:議事録の打ち合わせ件名
議事録のポイント1つ目は議事録の打ち合わせ件名です。
議事録の打ち合わせ件名は意外に大切です。
何故なら長期スパンで見た時に、活用される資料か否かが件名で決まると言っても過言では無いからです。(これは自動車メーカー勤務時代の一次情報です。)
打ち合わせ件名というのは議事録をPDFなどで保管する際のタイトルになることが多いです。
ということはよく分からない件名だと、必要な時に検索をかけても出てこないといった事態になりかねません。
例えば、AとBのタイトル、どちらが分かり易いでしょうか?
A:顧客打ち合わせ
B:Cプロジェクト 顧客 日程軸調整打ち合わせ
これは説明しやすくするための極端の例ですが、Aと「≒」のタイトルを付けている人は意外に少なくありません。
大切なポイントは「何の案件なのか」「誰と打ち合わせなのか」「何を打ち合わせしたのか」のキーワードをタイトルに散りばめることが大切です。
※参考ですが、各キーワードはチームや部署で共通のキーワードを定義しましょう。同じ内容を指し示すキーワードが複数あると、後々検索をかけて情報を引き出す時に大変です。
議事録のポイント2:打ち合わせ日時・時間・場所・参集者
議事録のポイント2つ目は打ち合わせ日時・時間・場所・参集者を明確にすることです。
議事録を書く際は打ち合わせ日時・時間・場所・参集者を必ず記載するようにしましょう。
どのタイミングで誰と話をしたのかは、エビデンスとして非常に重要な内容となります。
必ず、漏れなく記載するようにしましょう。
大所帯の会議の際は顔と名前が一致しないことや、誰が来ていたのかわからなくなることが多いです。
なので、会議室入口に会社/部署/氏名を記載頂く紙を準備し、記載頂いてから会議室へ入場して頂くように段取りしましょう。
議事録のポイント3:打ち合わせ目的
議事録のポイント3つ目は打ち合わせ目的を明確に記載することです。
議事録の打ち合わせ目的をあなたは何と書いているでしょうか?
ここでもAとBの例で考えてみましょう。
A:進捗について打ち合わせる
B:9/25から開始する、B案件の顧客納品の準備状況及び課題の有無を確認する。(例:確認内容 別紙P4/5参照)
議事録の書き方/まとめ方で大切なポイントは、「何を目的として打ち合わせをし」「何が決まったのか」ということです。
当然、抽象的な目的をしか持ち合わせていない打ち合わせは、抽象的な答えが導き出されます。
少し厳しいことを申し上げると、それでは打ち合わせをする意味が無いのです。
基本的な考え方として、鋭い問いからしか、鋭い答えは生まれません。
打ち合わせ前に必ず、自分自身に目的を問い、議事録に落とし込むようにしましょう。
議事録のポイント4:【議事録の最重要内容】日程軸の記載
議事録のポイント4つ目は最重要内容である日程軸の記載です。
国家レベルの研究機関から、自動車メーカーのような製造業、国民生活のインフラであるスーパーのような小売業まで、求められている日程軸の中で何が出来るかが問われるのが仕事です。
ほぼ全ての業種・業界において例外はありません。
皆さんが分かり易いと思われるスーパーを事例に考えてみましょう。
あなたがスーパーの仕入れ担当で、クリスマス用のチキンを仕入れたいとしましょう。
当然、スーパーで売りたいタイミングはクリスマス前日の12/24から当日の12/25です。
仕入れ先と要求単価・要求産地・要求数量等の項目を必死に調整して、調整内容が折り合った段階で、仕入れ先から「クリスマスまでの納品は無理です。早くて12/27納品です。」と言われたらどうでしょう?そこまでの打ち合わせ内容・時間と打ち合わせ議事録が全てパーです。
何やら笑い話のようですが、私がサラリーマン時代にこれをやっていた同僚がたくさんいます。
当然、優秀な上司にど叱られていました。笑
まず、一番最初に話をして、議事録の前提条件として合意しなければならない内容は日程軸なのです。
全体の進行や調達スケジュールを明確に記載するのはもちろん、個人レベルの宿題項目に対しても各項目ごとに日程軸を割り振って下さい。
日程軸を制するものは仕事を制します。
内部リンク:【自動車メーカーの日程表の書き方】日程表で押さえるべきポイント3つ
内部リンク:【日程・スケジュール管理のコツ】管理できない人が心がけるべきポイント7選
議事録のポイント5:議事録の結論
議事録のポイント5つ目は議事録の結論です。
この記事を読んでいる優秀な皆さんは必ず議事録には結論を書いていることでしょう。
念のため、正しく結論が書けているかおさらいしましょう。
議事録の結論のポイントは2つだけです。
- 確認・調整・合意出来た内容を記載
- 確定未完の場合や解答待ちの場合は内容と確認可能日程を記載
単純明快なので、特に特記要素はありませんが、気をつけないといけないことは、なるべく具体的に結論を書くことです。
日程軸の章でも使用したクリスマス用チキン仕入れの事例で考えてみましょう。(ちなみに私はチキンよりも海鮮が好きです。笑)
Aさんの議事録:「結論:クリスマス用のチキンの仕入れを合意した。」
Bさんの議事録:「結論:クリスマス用のチキンの仕入れについて、記載条件にて合意した。産地:国産、納入数:100式(匹)、仕入れ状態:冷凍、納入単価:500円/式、納入日時:12/23 14:00〜17:00間」
どちらの結論が分かり易いでしょうか?
Bさんの結論の方が分かり易いですし、お互いの認識の相違を無くすツールとして議事録が機能してくれますよね。
第三者が見て分かる内容になっているか、ポイントを網羅できているかは常に自分自身に問うようにしましょう。
議事録のポイント6:議事録への質疑応答の抜粋記載
議事録のポイント6つ目は議事録への質疑応答の抜粋記載方法です。
議事録に書いておきたい質疑応答の抜粋ポイントが2つあります。
- 当初の目的からは逸れた内容だが、記載すべきと判断した内容(今後、関連してくる可能性のある内容)
- 結論の布石となった内容や重要な調整プロセス
この項目はさじ加減が難しいところですが、上司から「何でこの結論になったの?」と聞かれそうな内容は、結論に至るまでの質疑応答プロセスを記載しておくというのが一つの目安になります。
上司や周囲の考え方の癖を観察しながら、記載内容をカスタマイズしてみて下さい。
議事録のポイント7:残課題及び今後の進め方
議事録のポイント7つ目は残課題及び今後の進め方を明記することです。
会議、議事録の終わりには必ず、残課題の有無と今後の進め方を記載するようにしましょう。
残課題は無いか?次のアクションは何か?を常に自分や相手に問い、言語化して共有しながら進める必要があります。
相手と進め方を共有することは、スムーズに仕事を進めるコツです。
また、自分の上司が知りたいのは「何かヤバイ課題は無い?」と「次はどんな日程で何するんだっけ?」です。
上司が知りたいことをきちんと議事録に記載するようにしましょう。
参考:会議のアンカリングテクニック

議事録に関連する内容なので、参考までに会議のアンカリングテクニックをお伝えしておきたいと思います。
打ち合わせや会議などで非常に大切なことは、会議の一番最初にアンカリングを打ってしまうことです。
会議の一番始めに、全関係者に対してアンカリングを打つと、話が脇道にそれにくく、自分が会議をコントロールし、議事録で明確に記載したい内容を重点的に話すことが出来るようになります。
小さなコツですが、効果は絶大なので、是非お試しあれ。
内部リンク:【会議の進め方】短い時間で効果を発揮する会議は何が違うのか?
議事録の書き方/まとめ方をマスターしよう!

最後まで読んでくださった方、ありがとうございました。
議事録の書き方/まとめ方をマスターして、是非仕事に生かして頂ければと思います。
最後に一番重要なポイントがあります。
自分の人生の目的、誰と何をするか、いつまでにどのようなアクションをするかなど。
そんな着眼点で物事を見てみると、面白くないでしょうか。
今回は以上です。
