こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- 部下、後輩社員の指導・育成で悩んでいる上司、先輩社員の方
- 指導・育成上手な人の方法論・コツを知りたい方
※この記事と併せて読みたい記事
内部リンク:【リーダーとは何か?】現代社会のリーダーに求められるもの
内部リンク:仕事の大失敗で立ち直れない人→使命:経験を未来の部下に伝える
内部リンク:【2030年予想図】今後、仕事で必要とされるスキルとは?
内部リンク:守備範囲が広い人は仕事ができる、ビジネスで成果を出す守備範囲
内部リンク:【遠回りが一番の近道】20代でした遠回りは30代以降で生きる
内部リンク:仕事で貧乏くじをよく引く人へ→長期的目線で見れば「大吉」
内部リンク:仕事での徹夜→20代前半に経験して徹夜を無くす仕組みを考える
それでは「ヨット講座」始めましょう。
※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterのフォロワー数は2021/1/18現在です。)

部下/後輩指導・育成は人の人生を変える

はじめに少し余談からお話させて下さい。
部下/後輩指導・育成は人の人生を変える力を持っています。
私は新卒で従業員1万人弱の自動車関連企業に入社しました。
自分で言うのもあれですが、入社した当初は典型的な「駄馬」であり、ダメ社員でした。
部署の新入社員歓迎会を「予定があるので行きません」とブッチぎり、入社式で新入社員数百名から選ばれた3名の代表を務めたことを鼻にかけているようないけ好かない社員でした。
干されていても一切不思議はありません。
いや、むしろ、干されなかったのが不思議なくらいです。(笑)
そんな私を温かく指導・育成して下さった、新入社員時代の先輩と上司には感謝しかありません。
今になって振り返ってみると、その先輩、上司の指導・育成方法は非常に緻密に計算されていたことに気づかされました。
世間には昔の私のような、いけ好かない部下や後輩社員を受け持ってしまった不幸な上司、先輩社員の方がいらっしゃることでしょう。 (笑)
この記事はそんな方に向けて、過去の自分自身への禊を兼ねて、お伝えしたいポイントをまとめました。
部下/後輩指導・育成は自分自身の資産

詳細の部下/後輩指導・育成のご説明に入る前に、もう一つお話をさせて下さい。
部下/後輩指導・育成は将来のあなたの資産そのものです。
それはなぜでしょうか?
現代社会では10年スパンで見ると、上司・部下の関係が逆転することは珍しくありません。(私が勤務していた重厚長大産業の大企業ですらそうなのですから、ベンチャー企業やIT企業では更にその傾向が強いことでしょう。)
更には独立も珍しくない世の中です。
要は今は部下であり、後輩なのかもしれません。
しかし、10年経ったら、上司や顧客になっている可能性は十分あります。
そうなった時に「何か恩返ししたいな」と思って貰えることはあなた自身の大きな資産になります。
人間というのは若い頃に丁寧に指導・育成してくれた人のことは忘れないものです。
私自身も未だに新入社員時代の上司・先輩には深く感謝しています。
将来的に「恩返ししたいな」と思って貰える指導・育成を心がけましょう。
部下/後輩指導・育成 6つのポイント
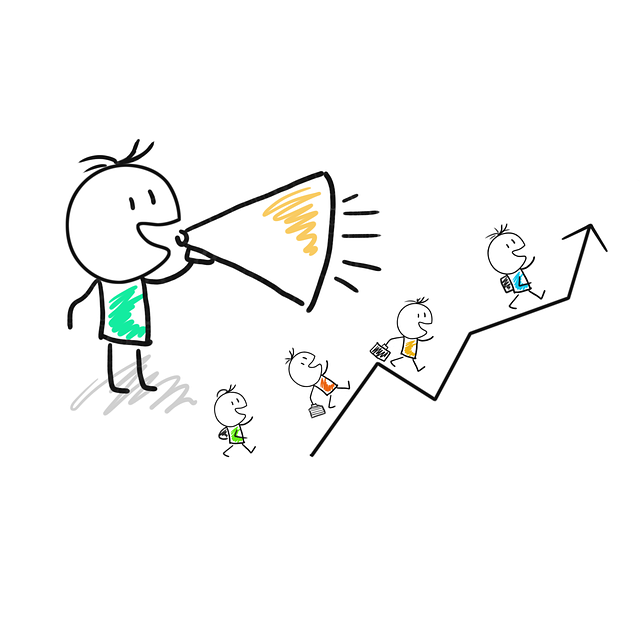
前置きが長くなり、申し訳ございませんでした。
ここからは部下/後輩指導・育成の6つのポイントをご説明していきたいと思います。
部下/後輩指導・育成のポイント1:指導・育成をする前に本人の言葉で語らせる
部下/後輩指導・育成のポイント1つ目は指導・育成をする前に本人の言葉で語らせることです。
部下/後輩を指導・育成する前に非常に大切なポイントがあります。
まず、これが出来ていない上司や先輩社員が非常に多いです。
例えるならば、プロ野球選手になりたいのに、ピアニストになるための指導・育成をされたら困りますよね?
この文章を読むと「その通り」だと思って頂けると思います。
しかし、会社で上記と同じようなことをやっている上司・先輩社員は非常に多いのです。
どうなっていきたいのかを語らせる
これは私が新入社員時代に指導して頂いた先輩社員から学んだことです。
会社の雰囲気にも慣れてきたある時、一緒に休憩をしていた先輩からこのような問いかけをされました。
「〇〇ちゃんは今後、どうなって行きたいとか、思いみたいなの何かあるの?」
私はこう答えました。「エンジニアとして使える社員になりたいです」と。
すると先輩は「じゃあ、俺が持ってるプロジェクトの〇〇案件を一つ主導してやってみるか?サポートはするよ。」と言って下さり、私は一つの案件を新入社員ながらメインで担当することが出来ました。
このように会話すると、上司/部下、先輩/後輩で考え方のギャップが生まれにくいですし、やらされ感も発生しにくいです。
部下/後輩指導・育成が上手く行っていない人はここで躓いているケースが非常に多いです。
これは大切なポイントなので覚えておきましょう。
同時に会社組織として要求する内容を提示する
一方で会社員である以上は、会社組織として要求される面倒臭いこともやらなくてはなりません。
会社組織として最低限要求することについては明確に提示しましょう。
部下/後輩指導・育成のポイント2:権限移譲し、「生簀の中で泳がせる」
部下/後輩指導・育成のポイント2つ目は権限移譲し、「生簀の中で泳がせる」ことです。
上司・先輩の中にはいきなり「放流」してしまう人が少なくありません。
もっと分かり易い言葉で申し上げるならば、「丸投げ」です。
これは絶対にNGです。
部下や後輩が潰れるパターンや転職してしまうパターンを観察すると、「丸投げ」パターンの比率がかなり高いように思います。
ポイントは2つです。
「自発的(能動的)に動ける環境を整えること」、「致命傷にならないように、常に守備範囲内にいるかを確認しておくこと」の2つです。
要は自分でやっている感覚を持たせて、経験を積ませながらも、外敵が現れた時には上司・先輩社員である自分が矢面に立つことです。
そのような姿を見た部下・後輩社員は将来同じことを出来るようになるでしょう。
そのような文化を作り上げることそのものが、上司・先輩社員の仕事なのです。
部下/後輩指導・育成のポイント3:常に観察し、声かけの天才になる
部下/後輩指導・育成のポイント3つ目は常に観察し、声かけの天才になることです。
指導・育成上手な上司・先輩社員は例外無く、「声かけの天才」です。
最近は部下・後輩社員の離職などに頭を悩ませている上司・先輩社員の方も多いのではないでしょうか?
更なるスキルアップやキャリアアップを狙って転職していくような優秀な社員は止めようがありませんが、せっかくいい感じに育ってきた部下・後輩が離職してしまうのは非常に勿体無いことです。
それを防止する一つの手段が声かけです。
声かけと言うと簡単に聞こえますが、実は非常に高度な技術です。
いつでもどこでも「〇〇ちゃん、元気?」みたいな声かけをするのは非常に簡単ですが(笑)、それでは意味がありません。
大切なポイントは普段から部下・後輩社員の雰囲気感や思考の癖を良く観察することです。
良く観察していると、必ず変化を察知出来ます。
「分からないことがあるけど、忙しそうだから声をかけにくいな」「これって上司に報告した方がいいレベルなのかな?」のような迷いは必ず雰囲気に現れます。
また、例えばですが、「レッドブルを飲んでいる時は疲れている時」のような思考の癖も洞察出来るでしょう。
そのような些細な変化を見逃さず、声かけすることです。
そのような普段の心がけが信頼関係に繋がり、組織の文化に染み込んでいくのです。
部下/後輩指導・育成のポイント4:上司/部下、先輩/後輩の組み合わせを工夫する
部下/後輩指導・育成のポイント4つ目は上司/部下、先輩/後輩の組み合わせを工夫することです。
いろいろと工夫しているが、なかなか伸びない部下や後輩に悩まれている管理職の方もいらっしゃるかと思います。
そのような時に見直してあげたいのが、上司/部下、先輩/後輩の組み合わせです。
綺麗事を抜きにすると、人には相性があります。
意図的にそのような組み合わせにすることは作戦としてはアリだと思いますが、伸び悩んでいるならば、組み合わせを変えてみることです。
一次情報として、いくつも見てきましたが、組み合わせを変えた途端、一気に爆発的に成長したパターンは枚挙に暇がありません。
上手くいけば、かなりの儲けものです。そんな発想も選択肢に入れておきましょう。
部下/後輩指導・育成のポイント5:自分のレベルを下げる
部下/後輩指導・育成のポイント5つ目は自分のレベルを下げることです。
これを読んで勉強しているあなたは優秀な方でしょう。
そんな優秀なあなたが認識し、留意しておくべきことがあります。
それは部下ごとに自分のレベルを下げて会話してあげるということです。
正直なところ、これを読んで勉強している優秀なあなたのレベルに部下が付いて来られる訳がありません。
あなた同様、ハイレベルな方と会話する場合は難しい横文字、ロジカルシンキングなどが非常に有効ですが、そうでない場合は全く理解出来ないことでしょう。
相手の語彙力や思考レベルに合わせながら、徐々に良さを引き出していく忍耐が必要です。
よくよく考えてみると、そもそも「名馬」は元々速いのです。
全員が「名馬」ならば、上司/先輩は用無しです。
「駄馬」を速く走らせるのが、ジョッキーであり、上司/先輩であるあなたの仕事だと心得ましょう。
部下/後輩指導・育成のポイント6:「タイミングの速さ」をしつこく指導する
部下/後輩指導・育成のポイント6つ目は「タイミングの速さ」をしつこく指導することです。
上司/先輩の方が部下/後輩にしつこく指導して頂きたい内容は「タイミングの速さ」です。
仕事の速さには3つあります。
この3つを部下・後輩に対して教え、「君はどれで勝負するのか?」と問うてみて下さい。
大体はタイミングの速さを選んでくるはずです。(「物理的な速さ」「思考の速さ」と回答する部下・後輩がいたならば、なかなか肝が座っています。笑)
スタートタイミングが速ければ、大体のミスはカバー可能です。
派手に失敗しまくった私が申し上げるのですから、間違いありません。(笑)
そんな日々の小さな習慣の部分を形作ることが部下/後輩指導・育成の第一歩なのです。
内部リンク:【仕事が速い人の特徴 9選】スピードアップの方法/コツ
部下/後輩は「時間差」で成長する!

最後まで、読んで下さった方、ありがとうございました。
時間が経った時に、下記のように、気付いてくれたら幸せではないでしょうか?
今回は以上です。
参考:オススメの本
オススメの本です。
伊庭正康さんの本は、時短術の本なども非常に面白いので、オススメの著者です。

