こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- ハイパフォーマーの習慣を知りたい人
- 人生を充実させている人の習慣を知りたい人
- 何となく20代を過ごしてしまった30代の人
※この記事と併せて読みたい記事
内部リンク:【ハイパフォーマーの習慣・特徴 7選】エンジニア・コンサルを分析
内部リンク:【現状打破したい人必読】仕事や人生で現状打破をする工夫 9選
内部リンク:仕事についていけないと思った時→3つのポイントを再確認しよう
内部リンク:仕事をしたくないと思った時のヒント→自分の視野を広げる
内部リンク:仕事で愚痴ばかりの人はあなたの成長を阻害するから近づかない
内部リンク:仕事で雑用ばかりという人へ→まずは雑用を完璧に仕上げること
内部リンク:【イラッとした時の対処法 3選】イラッとする人の行動・言葉
それでは「ヨット講座」始めましょう。
※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/3/25現在です。)

20代で身につけた習慣は人生を変える

これは大袈裟な表現ではありません。大企業2社で上司、同僚、後輩、取引先などを観察して確信した100%一次情報の事実です。
良い習慣を身につけている人は例外無く飛躍して行きます。
悪い習慣を身につけている人は例外無く零落して行きます。
これには例外は一切ありません。
20代で良い習慣を身につけた人と何も意識していなかった人の差は一生埋まりません。
残酷ですが、これが現実です。
しかし、今から少しでも何かを変えようとする姿勢が大切なのです。
20代、30代の人へのヒントになれば幸いです。
20代で身につけたい習慣 8選
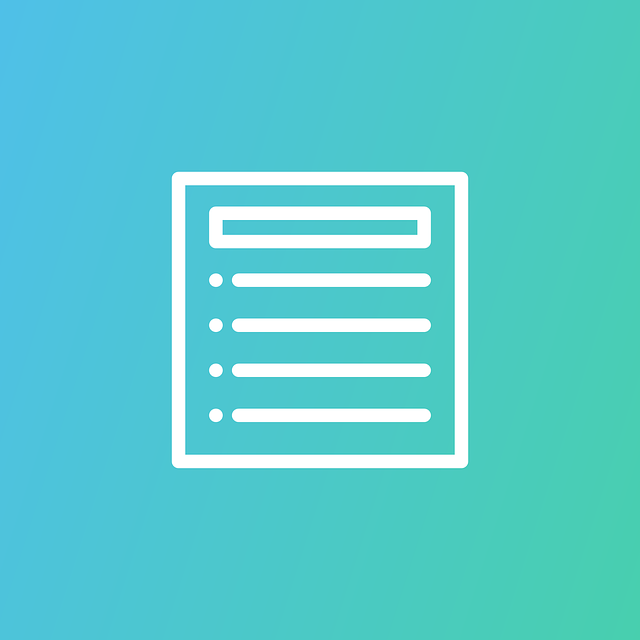
20代で身につけたい習慣を8つ厳選しました。
一つでも習慣化すれば、あなたの人生は大きく動き出すことでしょう。
それでは具体的な習慣の説明に入って行きましょう。
20代で必ず身につけたい習慣1:早起き
20代で必ず身につけたい習慣1つ目は早起きです。
自分の天才さで勝負できるようなフリーランスの方は何時に起きても構わないと思いますが、会社勤めの場合は確実に早起きを習慣にすることをおすすめします。
大切なポイントは仕事などで切羽詰まって単発的に早起きするのではなく、習慣として早起きするということです。
自身の一次情報からお話するならば、ハイパフォーマーや人生を充実させている人は遅くともAM5:30までには起きている人が多いです。
何をするかは人それぞれで、運動をする人、読書をする人、仕事をする人と様々ですが、人とタイミングをずらして活動を開始しています。
会社への出社も概して早く、朝から颯爽と出社し、シャキッとした目つきで仕事をしている人も数多いです。
そして、早い時間にスパッと帰社していきます。
逆に零落する20代は寝坊することが非常に多いです。
サラリーマン時代に遅刻している輩を複数見かけましたが、仕事でも「遅刻の常習犯」であったという事実は様々なことを考えさせられます。
遅刻の連絡を受けた当時の私の上司は「事故をしないようにゆっくり来なさい」と優しく言っていましたが、内心は呆れていたことでしょう。
(上司の心中としては「叱った結果、慌てて運転し、事故になったらそちらの方が大変だから」という理由だと推察しました。自動車メーカーだから尚更です。)
また、遅刻はせずとも、出社してしばらくはボケーっとしている輩もよく見かけました。
朝一から出社しているハイパフォーマーの上司に、出社した瞬間に質問攻めにされ、しどろもどろになっている輩も複数見かけました。
そして、そのような輩に限ってダラダラと残業しています。(更に仕事と関係ないことをベラベラ喋っています。)
どの角度からどのように考えても、どちらが良い習慣なのかは一目瞭然だと思います。
早起きすると様々なことに気付きます。
- 通勤時間が短縮される。(車通勤の場合)
- 人口密度が低く、快適である。
- 夏に朝一出社をすると汗をかきにくく、快適である。
- 静かで優雅な時間が流れている。
- 小鳥の囀りが聞こえ、幸せな気分になれる。
- 誰がどのような順番で出社しているかを把握でき、パフォーマンスとの因果関係を考察することができる。
このような様々なことに気づける感性を若いうちに育むことが非常に重要なのです。
人間は気づかないと変われません。
その気づき、何かを変化させるための手段が早起きなのです。
10年続けると確実に人生が変わることだけは間違いないです。
一次情報でたくさん見てきましたから。
朝型のメリットは別の記事で解説していますので、ご一読下さい。
内部リンク:【生活リズム:朝型のメリット】ハイパフォーマーはなぜ朝が早いのか?
※この項目に関連する記事は別記事にもまとめていますので、興味のある方はご一読下さい。
内部リンク:【存在感がないと感じている人へ】会社で存在感のある人の特徴 7選
内部リンク:【仕事が速い人の特徴 9選】スピードアップの方法/コツ
内部リンク:【期限遵守・厳守は人生の本質】期限を守れない人が意識すること
20代で必ず身につけたい習慣2:読書
20代で必ず身につけたい習慣2つ目は読書です。
内部リンク:【読書ができない、苦手な人へ】人生を豊かにする本の読み方のコツ
内部リンク:【本の楽しみ方】人生を変えるおすすめの本の楽しみ方 5選
これは読書好きの私のバイアスがかかっていますが(笑)、一次情報でも実証されているので、間違いありません。
零落する20代はTV鑑賞を習慣にしています。
99%の飛躍する20代は読書を習慣にしている人ばかりです。
小説を読む人、ビジネス書を読む人、哲学書を読む人、専門書を読む人。
色々MIXして読む人など様々ですが、例外なく飛躍しているのです。
何故だろう?と真剣に考えたことがあります。
たどり着いた答えは3つです。
- 1つ目は語彙力が磨かれるということ
- 2つ目は仮説創造力が磨かれるということ
- 3つ目は成功者の共通言語は読書であるということ
語彙力が磨かれる
読書というのは視覚情報のみなので、言葉のみで全てを表現する必要があります。
TVやYouTubeのように動き、音、色などで人間の本能を刺激することは出来ないです。
同じことを言っていても「深く心に刺さるか」、「分かり易いか」などは、語彙力で雲泥の差が出てきます。
1つの実話をご紹介しましょう。
例えば、プラスチック部品製造用の金型に特殊なコーティング加工をかけたとしましょう。それを何も知らない女性スタッフに説明する必要が発生したと仮定します。
Aさんは「これはバイコートというコーティングでふっ素樹脂、シロキサン樹脂、スーパーエンプラなどの潤滑性・離型性に優れた有機系材料を組み合わせた複合有機系のコーティングシステムです」と説明しました。
Bさんは「ティファールのフライパンはこびりつきにくいですよね?あれの樹脂金型バージョンです。」と説明しました。
どちらが分かり易かったでしょうか?
科学エンジニアでもない限りはBさんの説明の方が分かり易いのではないでしょうか?
Aさんは読書の習慣が無い人です。
Bさんは読書の習慣がある人です。
上記は実話に基づいた例え話ですが、上司への説明でも、お客様への説明でも、全く同じことが言えます。
要は相手に伝わる語彙力が大切なのです。
伝わるか、否かの分かれ道が語彙力の差なのです。
仮説想像力が磨かれる
これは小説を読む人なら分かると思いますが、小説を読んでいると先の展開を予測します。
「こうなるのではないか?」とか「こんな風に繋がってくるのではないか?」などと仮説を立てて、読み進めるはずです。
小説であれば、その仮説が裏切られながらも、うまく繋がっていると感動する訳です。(少なくとも私はそうです。笑)
また、伏線が繋がった時に前のページに舞い戻って、「ここから繋がっていたのか!」と読み直してしまう人もいるでしょう。(完全に小説マニアですね。笑)
これは仕事能力とは一見関係ないように見えます。
いいえ、実は非常に関係性が高いのです。
更にどこを起点にこの結果に繋がったのか?を思考する習慣は非常に重要です。問題や課題の起点が分からないと解決しようがありませんし、暫定的に解決したとしても必ず再発してしまいます。
分かってきたでしょうか?
仕事能力とは小説の仮説創造力と同じなのです。
たとえ、その人にとっては「娯楽」だとしても、日々仮説創造力を磨いている人とそれ以外の人とは差が出て当然なのです。
内部リンク:【小説の楽しみ方】人生を変える小説の楽しみ方 5選
成功者の共通言語は読書である
一流企業の部長や課長クラスであれば、当たり前のようにOFFJTで読書を習慣にしている人が多いです。これは一次情報でも確認しています。
自動車メーカー勤務時代の部長は読書家でしたし、取引先の設備メーカーの社長も読書家でした。
読書家からすれば、様々な人の思考パターン、行動パターン、語彙力で何をどれくらい読んでいるのかが、手に取るように分かるのです。
事象としてどうなるかと言えば、依怙贔屓して頂けます。
これは100%ノンフィクションの事実です。(なぜなら私が部長に依怙贔屓して頂けた事実を身を持って体験したからです。笑)
出世の決め手や困った時に助けて貰えるかどうかは、「普段読書をしているか」で決まると言っても過言ではないのです。
一方で零落する20代の習慣について少し考えてみましょう。
見ているものと言えば、TVかYouTubeのバラエティ番組です。
そこから生まれるものは、「下世話なゴシップネタ、愚痴、悪口、噂話、〇〇らしい」と言った2次情報です。
もうこれ以上説明する必要も無いでしょう。
どちらを習慣にするかは、あなた自身が決めれば良いです。
20代で必ず身につけたい習慣3:コソコソ話をしない
20代で必ず身につけたい習慣3つ目はコソコソ話をしないことです。
飛躍する20代はコソコソ話をされる側。零落する20代はコソコソ話をする側。
千田琢哉さんの本を読んだ時にこのことに気づき、笑ってしまった記憶がある。(千田琢哉さんを知らない人は検索して本を購入してみて欲しい。20代の必読書です。)
飛躍する20代は何かと必死ですし、向上心剥き出しです。
なぜならば、周りとは異なる景色が見えているし、周りとは異なる未来が見えているからです。
そんな零落する20代の習慣は、飲み会の一次会ではくだらない話で盛り上がり、2次会ではいない人の悪口に精を出しているようです。(私は一次会は90%以上の確率で欠席、二次会には100%行かないので、周りから聞いた二次情報ですが。)
「惰性でコソコソ話をすることが習慣の人」と「一人読書をしたり、運動したり、映画を見たりして、様々な勉強を積み重ねることが習慣の人」のどちらが成長するか?という話なのです。
これを読んで勉強している優秀なあなたには、申し上げなくても分かるはずです。
社会人になって、1年や2年でこの事実に気づき、抜け出せた人は猛烈に努力すれば逆転する可能性があると思います。
しかし、5年、10年と時が過ぎると、良い習慣を身につけた人との序列は100%逆転不可能です。
20代前半から習慣にした5年、10年というのは「宇宙レベル」の大きさと考えるべきです。
この内容の非常に恐ろしいところは、零落する習慣を続けても、30歳前後になるまで明確な差が出にくいということです。
「給料」「役職」「転職」「独立」など、何らかの要素が大きく変化する可能性が高いのが30歳前後です。
零落する20代も何かのタイミングで「ヤバイ」と気づき、慌てて努力を始める人が現れますが、末期癌のようなもので、手遅れなのです。
そして、更にコソコソ話の習慣に精を出し、優秀な同僚や優秀な後輩の足を引っ張るという構図になってしまう訳です。
これを読んでヒヤッとした人は今すぐに改めることが大切です。「たった今」からです。
もう30代であろうと、40代であろうと、習慣を改めることです。
逆転は100%不可能ですが、習慣を改めれば、「優秀な人の一派で働く仲間」に入れて貰える可能性はあります。
※この項目の関連記事は以下です。興味のある方はご一読下さい。
内部リンク:自分は仕事ができないと思ったら→できない人の口癖を口にしない
内部リンク:飛躍を目指す20代がやるべきこと→結論:様々な勉強、体験
20代で必ず身につけたい習慣4:整理整頓の徹底
20代で必ず身につけたい習慣4つ目は整理整頓の徹底です。
会社のデスク、デスクの机の中、パソコンのデスクトップ画面、スマホのホーム画面のアプリアイコン、自宅の部屋、自宅の物、人間関係と挙げ始めたらキリのないくらい整理整頓を徹底して習慣にしています。
仕事とは何でしょうか?それは整理整頓そのものです。
資本主義社会の仕組みとして、これは絶対原則なのです。
非常にシンプルに考えると、儲かる仕組みを整理整頓することが仕事だからです。
儲かる仕組みを整理整頓するとはどういうことでしょうか?
儲けるためには、儲かる仕組みを整理して取捨選択することです。
必要/不要を判断して取捨選択することです。(→整理)
必要なことは標準や基準、フローチャートに落とし込み、仕組み化することです。(→整頓)
センスの良い方はもう理解したと思いますが、仕事とは整理整頓の習慣そのものなのです。
会社のデスクや、自宅の部屋すら整理整頓出来ない習慣の人間が飛躍出来るはずがないのです。
100%ノンフィクションの実例を挙げて考えてみましょう。
自動車メーカー勤務時代の部長の机やパソコンのデスクトップ、引き出しの中、ふと見えたメールフォルダはいつも常軌を逸するくらいに綺麗でした。
「1日100件単位で書類が上申されてくるのに」「何百件ものメールが送信されてくるのに」です。
これほどに大量の書類やメールが回ってくる130名の部を束ねる部長がやれるのですから、平社員がやれない理由などどこにもないのです。
当然出世頭で自動車メーカーでも次期役員候補だった方です。(自動車メーカーを退職した今でも尊敬しています。)
逆にパッとしない係長の机はいつもくちゃくちゃでした。
こちらが定点観測して、1日後に埋もれている書類を探し出して、一番上に置き換える「習慣」が必要だったくらいです。(笑い話のようですが実話です。笑)
当然、パソコンのデスクトップアイコン、デスクの机の中、スマホのアプリアイコンは常にくちゃくちゃでした。
メールの未読数は1,000件を超えており、「怪しいサイトにでも登録して勧誘メールが大量に送られて来ているのか?」などと想像してしまったくらいです。(笑)
自分の管理を習慣に出来ていない人間が、部下を育てられるはずがありません。
そのような上司の口癖が「人は勝手に育つもの」でした。
「おいおい、マジかよ、この人」と心の中で思っていたことは今でも忘れないです。(笑)
日常や仕事で整理整頓が習慣的に出来るようになれば、必然的に思考の整理整頓も出来るようになりますし、行動の整理整頓も出来るようになります。
嘘だと思ったあなたは、そのままでいいです。
いつも時代も何か自分から習慣を変えようとした人だけが、成長していくのがこの世の中の仕組みなのですから。
※整理整頓は別記事でも詳細を解説していますので、興味の湧いた方はご一読下さい。
内部リンク:【現代の必須スキル→情報5S、整理整頓】錯綜する情報のまとめ方
内部リンク:【整理整頓が苦手、できない人は必読】家庭、仕事での整理整頓のコツ
内部リンク:【シンプルは美しい】シンプルライフを送るための4つの着眼点
20代で必ず身につけたい習慣5:事務のおばちゃんを大切にする
20代で必ず身につけたい習慣5つ目は事務のおばちゃんを大切にすることです。
飛躍する20代は「事務のおばちゃん」に丁寧に接することを習慣にします。
零落する20代は「事務のおばちゃん」に横柄に接することを習慣にします。
これは社内ではなく、取引先を見て、気付いたことです。
東証一部上場企業2社では「事務のおばちゃん」に横柄に接している人は皆無に等しかったです。
何故なら、事務のおばちゃんが隠れた最高権力者であることが珍しく無いからです。(笑)
部長や役員が出世する前に面倒を見て貰っていたり、他部署のおばちゃんとの独自ネットワークを持っており、それで問題が解決したような例も多々あるからです。
冗談かと思うかもしれないですが、1次情報であり、事実です。(笑)
このような恐ろしい情報は代々新入社員に引き継がれていくので、勤めていた会社で事務のおばちゃんに横柄に接する人間はまず見たことがありません。
しかし、取引先を見ていると、取引先の担当者にはペコペコしているのに、事務のおばちゃんには横柄な人が結構いるのです。
それを見ているこちらとしては、恐ろしいことをしているなとつくづく思うのです。
何故か?
その事務のおばちゃんが「隠れた権力者」である可能性は十分あるからです。
少し考えてみましょう。
その事務のおばちゃんが東証一部上場企業役員の奥さんかもしれないです。
その事務のおばちゃんの息子が東証一部上場企業の社員かもしれないです。
その事務のおばちゃん自身が地主で影の権力者かもしれないです。
思っている以上に世の中は狭いものです。
事務のおばちゃんも大人なので、軽く受け流してくれているのかもしれないですが、我慢の限界を超える出来事があったとしましょう。
我慢の限界を超えたときに東証一部上場企業役員の旦那さんに愚痴るかもしれない。東証一部上場企業勤務の息子さんに愚痴るかもしれない。知り合いの権力者に愚痴るかもしれない。
そうすると何が起こるのでしょうか?
関係会社であれば、何かのタイミングでその会社の重役に注意がいくでしょう。
もしくは取引を打ち切られるかもしれないです。
また権力者から手が回されて、完全犯罪が如くクビになるかもしれないです。
笑い事のようですが、実際にあった内容に少々面白おかしく脚色した事実なのです。
知らないということは恐ろしいことです。
そうすれば、「完全犯罪」に遭う可能性はほぼ0%まで下げることができます。
もちろん失礼な対応をされた場合などは、きちんとクレームを入れるべきです。
ただ、相手は丁寧な対応をしているのに、自分が横柄になるべきではないのです。
「事務のおばちゃん」を大切にすることを習慣にしましょう。
20代で必ず身につけたい習慣6:数字や絵を用いて説明する
20代で必ず身につけたい習慣6つ目は数字や絵を用いて説明することです。
飛躍する20代は数字や絵で説明することを習慣にします。
飛躍する20代の特徴は数字や絵で説明するのが非常に上手いということです。
「数字や絵が表現出来る、書ける」=「自身が理解している」ということです。
「数字や絵が表現出来ない、書けない」=「自身が理解していない」ということです。
これには例外はありません。(絵の上手い下手はあると思いますが。)
私が新卒で新入社員の頃に指導員だった先輩がものすごく教え上手な方でした。
その先輩の特徴と習慣を分析したところ、とにかく「数字や絵で表現する」ことが恐ろしいくらいに上手でした。(他にも素晴らしいところだらけなのですが、ここでは割愛させて頂きます。今の私の土台を作ってくださった方です。油圧・空圧・金型・真空・接着剤等々全ての事柄を絵で表現出来る方だった。)
その新入社員に向かって、専門用語や言葉を連発しても、本質的な意味での理解度は非常に低いものとなってしまいます。
そこで出番になるのが、「数字や絵」なのです。
「数字や絵」を使用すれば、「言葉と意味」、「言葉と物」が結びついて理解しやすくなります。
また、不明点を質問する際にも、絵の具体的な部分を指しながら質問出来るので、お互いのコミュニケーションミスが圧倒的に減ります。
このように、お互いの「時間密度」を高め、的確に指導する習慣があるのが、「飛躍する先輩」です。
一方、新入社員に向かって、専門用語のみを連発するのが、「零落する20代」である。
「言ったよね?」が口癖の「零落する20代」の先輩に付いた新入社員は成長が遅くなってしまいます。
新入社員が全く同じ能力でも「飛躍する20代」の先輩に付くか「零落する20代」の先輩に付くかで、その後の人生が大きく変わるのが大企業の恐ろしいところです。(少なくとも私はそう感じました。)
自分の理解が足りないのは勝手ですが、後輩の未来を間接的に邪魔する習慣は「合法的な犯罪」です。
今日から「数字と絵」を使用して説明することを習慣にしましょう。
PS.
「数字と絵」で説明する習慣は、海外出張に行った際に抜群の強さを発揮します。
言語が弱い人(私がそうだった。)は数字と絵で説明する習慣を付けておくと、ローカルスタッフとコミュニケーションが図りやすくなるからです。
海外3カ国で私が実践した実話です。
内部リンク:仕事で初めて海外出張へ行く人へ:海外出張前の準備、仕事の進め方
20代で必ず身につけたい習慣7:上司に「意見」を述べる
20代で必ず身につけたい習慣7つ目は上司に「意見」を述べることです。
飛躍する20代は上司にも意見を言うのが習慣です。
零落する20代は上司の陰口を言うのが習慣です。
飛躍する20代と零落する20代の最も大きな違いの一つが上司への対応です。
「飛躍する20代」は上司に面と向かって意見を言うことが習慣です。
その代わり、陰口は一切言いません。
「零落する20代」は上司の目の前ではひたすら頷くのが習慣です。
その代わり、陰口をコソコソと話します。
※念のため補足しますが、「意見を言う」と「歯向かう」はきちんと区別していただきたいです。サラリーマンで上司に「歯向かう」と100%干されます。
「飛躍する20代」は自分の意見をきちんと表現することが習慣です。
意見を言うことは、思考を言語化して表現することであり、周りの意見を引き出す潤滑油的な意味合いがあることをよく理解しているからです。
合っているか、間違っているかなど大した問題ではないこともよく分かっています。(あまりに考えていない意見は「アホか」と思われるので、お気をつけていただきたいですが。)
「零落する20代」は自分の意見に自信がないです。
「否定されたらどうしよう」ばかりを考えています。
その上、上手く言語化出来ないので、「陰で同レベルの仲間に愚痴って発散する習慣」という構図なのです。
意見をハッキリと言うと生意気に思われる節があるかもしれませんが、全く問題ないです。
きちんと自分の目線や周囲の目線も鑑みた意見を言い、表裏がない人物は間違いなく周囲から応援されるし、チームの中核人物になるはずだからです。
※繰り返しますが、「意見を言う」と「歯向かう」はきちんと区別することです。
逆に意見は言わないが、陰でコソコソと上司の陰口を言うのが習慣の人物はどうでしょう?
100%周囲から見下されるでしょうし、同レベルの「Cチーム」としか関われなくなります。
また、上司の耳に入れば、完全犯罪が如く干されるに違いありません。
以上の話を聞いてどちらを習慣にするかはあなたの自由です。
20代で必ず身につけたい習慣8:自分で判断、決断する
20代で必ず身につけたい習慣8つ目は自分で判断、決断することです。
飛躍する20代は自分で判断、決断する習慣を持ち合わせています。
零落する20代はひたすらいろんな人に相談します。
まずは「判断」と「決断」からおさらいしましょう。
「判断」とは客観的に見て正しいことを選択するということです。
すなわち客観で取捨選択して整理するということです。
「決断」とは主観的に見て正しいことを選択するということです。
すなわち主観(=自分)で選択するということです。
飛躍する20代は自身で判断・決断することを習慣にします。
ディベートのような思考でメリット・デメリットを整理し、客観的に判断するのです。
(ディベートについて勉強したい方は瀧本哲史さんの「武器としての決断思考」を是非読んでみて頂きたいです。非常に勉強になります。)
その後、自分がやりたい事か?好きになれそうか?などの主観的な要素を加え、「決断」する訳です。
この工程を当たり前のように自分自身と向き合って行う習慣があります。
他者から何か言われたとしても、参考にはしますが、自分で判断・決断します。
一方、零落する20代はどうでしょうか?
零落する20代は不満が多く、いつもいろいろな人に相談しています。
「こんな不満がある」とか「どうしたら良いでしょう?」といつも様々な人に相談することを習慣にしていますが、解決している姿や、転職/独立をした姿を少なくとも私は見たことが無いです。
恐らくですが、相談することが目的になっており、何かをする「ふり」を習慣にしているのです。
本気の人はハイパフォーマーの先輩や上司、もしくは信頼している人1名に相談して、とっとと自分で判断・決断して進めています。
これが世の中のありのままの現実なのです。
20代だから、ギリギリ許されていますが、将来を想像してみましょう。
将来、経営者、リーダー、マネージャーになった際に決断が出来なかったらどうでしょう?
絶対に部下から信用されないでしょうし、「こいつの下で働きたくないな」と思われるに違いありません。
経営者、リーダー、マネージャーの仕事は決断して責任を取ることです。
それ以上でもそれ以下でも無いのです。
自分自身で判断・決断をする習慣が無い人に飛躍が出来るはずがないのです。
とにかく、何でも自分で決める習慣を付けることです。
別にいきなり転職、独立をして下さいと言っている訳ではないです。
旅行先、購入したい物、読みたい本など小さなことから自分で決める習慣で十分です。
自身で判断、決断する習慣を付けましょう。
内部リンク:【決断力は人生を豊かにする】決断できない人に贈りたい言葉
20代で良い習慣を身につけ、人生を変えよう!

最後まで読んでくださった方、ありがとうございました。
習慣には人生を変える力があります。
内部リンク:【人生・転職が上手くいく人の特徴→タイミングを逃さない】
10年後にこの言葉の意味が分かるはずです。
ご健闘をお祈りしております。
今回は以上です。


