こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- 「継続力がない」と悩んでいる人
- 「継続するには何が必要なのか」と悩んでいる人
- 継続するためのコツを知りたい人
※この記事と併せて読みたい記事
リンク:【0から1を生み出す人が仕事のできる人】0から1をつくる方法
リンク:【努力が報われない人、努力できない人必読】効果を発揮する努力法
リンク:【人生に一発逆転はない】一発逆転の方法を考え始めたら危険信号
リンク:【真面目な人が損をする理由】社会的地位の高さ=損をすること
リンク:【無形資産を保有する個人が強い時代】無形資産の作り方、具体例
それでは、「ヨット講座」始めましょう。(※ヨットはこんな人です。Twitterフォロワー数は2020/11/30現在です。)

はじめに:継続力とは何か?

はじめに継続力とは何かについて考えていくことにしましょう。
継続力とは?→実施した内容を引き続き行うこと
まず、継続力の言葉の定義を明確にしていきましょう。
継続力とは「実施した内容を引き続き行うこと」を指します。
まず、ここから興味深い考察が出来ます。
自分ができないことは「継続」、「行動」のどちらかを見極める
まず「継続できない」、「継続力がない」という人が考えるべきことがあります。
継続力とは「実施した内容を引き続き行うこと」というのは前述しました。
「継続できない」「継続力がない」という人に対して、立てられる仮説の一つは行動の絶対量が少ないのではないかという仮説です。
人間には向き不向きが存在します。
3つ試して、3つとも継続できないというのは特に不思議なことではありません。
継続力がある人を虚心坦懐に観察してみると、2つのポイントに気付かされます。
一つ目は行動の絶対量が多いことです。少ない人でも10個程度、多い人だと100個程度試しています。
要は行動を起こし、自分は何なら継続出来るのかをきちんと実体験で確認しているということです。
2つ目は意外に継続していること以上に継続していないことが多いという事実です。
合わないもの/ことは継続しないという発想です。
もし、あなたが「私に足りないのは行動力だ」と思った場合は以下の記事にまとめてありますので、ご一読下さい。
継続力→目的ではなく手段
「継続」というのは、自分が継続的に成長すること、自分が幸せになるための手段に過ぎません。
その事実をきちんと押さえておくことが大切です。
客観的に正しくないと思われる習慣を継続したり、継続することによって自分が息苦しくなってしまうのであれば、本末転倒です。
自分は何を目的に、どのような未来を切り開いていくために何を継続するのか?と考えてみると意外に深い問いになります。
目的を明確にした上で、正しい手段を選択し、継続する。
読者の皆さんが知りたいことから少し論点がズレているかもしれませんが、これは大切な発想なので覚えておいて頂ければと思います。
継続力→人間のみが持つ概念
少し余談です。
AIやロボットはアルゴリズムやプログラムされた通りに淡々粛々と動作します。
動物は本能に応じて、淡々と起床し、生きるために必要な狩りを行い、生殖などをします。
このような事例で分かるように「継続力」は人間のみにある概念なのです。
継続力が無いのは「本能がやりたくない」と言っているから。
そんな風に考えてみると、また新たな発見があるのかもしれません。
継続できない理由と継続のコツ 6選
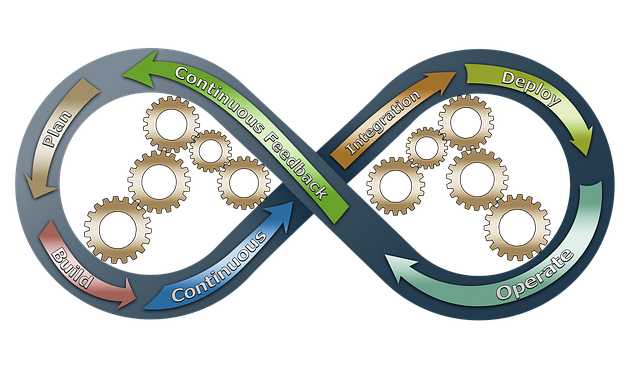
ここからは継続できない理由の分析と継続のコツをご説明していくことにしましょう。
継続できない、継続力がない理由1:目的が不明確
継続できない、継続力がない理由1つ目は目的が不明確であるということです。
何を目的にその継続をしているか?と問われた時に答えられないのです。
目的が不明確だと、苦しい状態に陥った時やイレギュラーな状態に陥った時に確実にあやふやになり、継続できない状態に突入してしまいます。
継続のコツ1:目的を明確にする
目的が明確だと、苦しい状態に陥った時やイレギュラーな状態に陥った時にも「目的」という軸をベースにどのような形で継続出来るかを考えることが出来るのです。
継続について悩む前に、目的について考えてみるようにしましょう。
※目的を考える上で身につけたい思考法は別の記事を解説していますので、興味のある方はご一読下さい。
継続できない、継続力がない理由2:苦手なことを継続しようとしている
継続できない、継続力がない理由2つ目は苦手なことを継続しようとしていることです。
基本的にいきなり苦手なことに挑戦しても継続できません。
継続のコツ2:好きなこと、得意なことから始める
逆説的に考えると、継続のコツは好きなこと、得意なことから始めるということです。
まずは、好きなこと、得意なことで継続を目指すことです。
その分析結果を基に苦手なことを継続することにチャレンジすることです。
このようなプロセスを踏んでいないと、「継続できない」「継続力がない」という負のスパイラルに陥ってしまいますので、ご注意下さい。
リンク:【苦手な人がいる・苦手なことがある人へ】結論→苦手は克服しなくてもいい!
継続できない、継続力がない理由3:ハードルを高く設定しすぎる
継続できない、継続力がない理由3つ目はハードルを高く設定しすぎることです。
例えば、読書初心者が読書を習慣にしようとした時に、難解な哲学書から読み始めるとまず間違いなく挫折します。
早起きをしたことが無い人が毎朝AM5:00に起きようとすると、よほど意志の強い人以外は挫折します。
これは非常に勿体ないことです。
継続のコツ3:ハードルを低くして、まずは継続
継続のコツはまずはハードルを低めに設定することです。
読書初心者は堂々と漫画で哲学を学べばいいですし、早起き初心者は今までより30分早く起きる習慣作りから始めれば良いのです。
もし難易度を上げて、難しいなと思ったら元に戻して続ければいいのです。
リンク:【読書ができない、苦手な人へおすすめの読書方法】人生を豊かにする本の読み方のコツ
リンク:【生活リズム:朝型のメリット】ハイパフォーマーはなぜ朝が早いのか?
継続できない、継続力がない理由4:同僚、友達と群れている
継続できない、継続力がない理由4つ目は同僚、友達と群れているからです。
この項目は少し厳しいので、読み飛ばして頂いても構いません。
そして、その群れている会社の同僚や友達と同じレベルの継続力になっていきます。
その会社の同僚や友達の継続力が高ければ良いのですが、群れている人というのは継続力が低い場合がほとんどなのが現実です。
なぜなら、自分の実力、継続力が無いのを群れて誤魔化そうとするからです。
真剣に継続できるようになりたいのであれば、この本質は避けて通れません。
継続のコツ4:同僚、友達と群れない
私は本質的に継続・成長するには2つの選択肢しかないと思っています。
1つ目は自分よりレベルの高い環境に飛び込むことです。
レベルの高い高校や大学というのは基本的に一部の天才を除いて継続力の塊のような人ばかりです。
また、従業員1万人弱以上の大企業も基本的に継続力の塊です。
そのような環境に飛び込めば、様々なことを継続するのは当たり前です。
自ずと自らも継続せざるを得ません。
この1つ目の方法は入学や入社のハードルもあるので、なかなか難易度が高いです。
すると必然的に2つ目の方法になります。
2つ目は孤独になることです。
孤独になると必然的に自分と向き合うことになりますし、愚痴を言う相手もいません。
孤独になると、時間が増えて勉強できますし、雑念や不要な情報が入って来にくくなります。
孤独になると継続出来る確率が上がるのです。
会社の休憩所で喫煙しながら、だべっている人に継続力のある人はいません。(タバコという喫煙習慣という意味では天才的な継続力を発揮しています。)
少し厳しいですが、そんな事実を知っておくことも継続する上でのヒントになると思います。
リンク:【友達はいらない】友達がいないけれど充実している人の考え方
継続できない、継続力がない理由5:言語化できていない
継続できない、継続力がない理由5つ目は言語化できていないことが多いことです。
継続するためには「言語化」することが欠かせません。
よほど意志の強い人以外は紙に書いて部屋に貼ったり、パソコンで資料を作成するなどして、言語化しないと継続することは難しいでしょう。
継続のコツ5:言語化、見える化を徹底する
継続のコツは言語化、見える化を徹底することです。
少し脇にそれますが、偉大な芸術家達が凄いのは「言語化」だけでは伝えられないことを絵画や彫刻などを通じて完璧に表現したからです。
彼らの場合は絵画や彫刻などを通じて継続、言語化、見える化をしている訳です。
天才ではない自覚のある人は、「言語化」→「意識化」→「習慣化」の流れを意識し、癖付けすることは非常に大切です。
まずは紙に書いて部屋に貼ったり、パソコンで資料を作成するなどして、言語化することです。
そして、それを毎日見る仕組みを作ることです。
リンク:【仕組み化の方法】自動車メーカーはなぜ強いのかを2つの軸で解説
継続できない、継続力がない理由6:整理整頓ができていない
継続できない、継続力がない理由6つ目は整理整頓ができていないことです。
継続するということは日々のやることが整理整頓できているということです。
頭の中の状態は部屋、パソコンのデスクトップ、スマホのホーム画面など様々な場所に顕在化します。
私はできないと思います。
継続のコツ6:整理整頓を徹底する
継続できている人というのは身の回りの整理整頓が徹底されています。
身の回りの整理整頓状態はそのまま思考の整理整頓状態です。
まずは身の回りの整理整頓から。そして最終的には思考の整理整頓へ。
これを覚えておきましょう。
様々なことを継続する上で非常に大切な発想です。
リンク:【整理整頓力】家庭、仕事で能力を発揮する人の6つの考え方
継続力は人生を好転させる

読書の継続、早起きの継続、思考習慣の継続。
10年、15年単位で積み重ねたことは自分の大きな資産になっています。
この記事を読んだ皆さんが「継続」できるキッカケを掴んでいただけていれば嬉しいです。
今回は以上です。
※この記事を読んだあなたにおすすめのその他の記事
リンク:【当事者意識を持つと仕事での成長が早い】当事者意識を持つ/持たせるには?
リンク:【挑戦が怖い、挑戦できない人へ】挑戦する心、勇気を養う思考法
リンク:【成長するには?→他責思考を改善しよう!】他責思考改善のヒント
リンク:【ブログのメリット 8選】個人におすすめの自己研鑽→ブログ
