こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- 仕事で上司に「当事者意識を持て」と怒られた人
- 仕事で当事者意識を持つには何が必要かを知りたい人
- 仕事で部下に当事者意識を持たせるには何をしたらいいのかを知りたい人
※この記事と併せて読みたい記事
内部リンク:モチベーションが上がらない、下がる場合は自分の視野を広げよう
内部リンク:仕事をしたくないと思った時のヒント→自分の視野を広げる
内部リンク:仕事でありえないミスを連発→再発防止の仕組み化で価値を生もう
内部リンク:仕事で貧乏くじをよく引く人へ→長期的目線で見れば「大吉」
それでは「ヨット講座」始めましょう。(※ヨットはこんな人です。Twitterフォロワー数は2020/11/30現在です。)

はじめに:当事者意識とは?

はじめに当事者意識とは何か?について考えていきましょう。
当事者意識→自分が関係すると認識している範囲、自覚
当事者意識とは自分の意識の中で「自分が関係すると認識している範囲、自覚」のことを言います。
例え話ですが、チームミーティングでりんごが売れない理由について考えていたとします。
あなたの担当はみかんであれば、りんごが売れない理由については興味が無く、当事者意識が低くなるということが起こりがちです。
逆に「りんごが売れない理由を紐解けば、自分の担当であるみかんも連動的に売れるはずだ」と自分事として考えられるのが当事者意識が高い人です。
当事者意識を言い換えると→抽象度の適応範囲
例えですが、自分が在住している区や市のことのみ考えている人を「当事者意識が低い」と定義するならば、日本や世界のことを考えている人は「当事者意識が高い」ということになります。
- 抽象度低:区、市
- 抽象度中:日本
- 抽象度高:世界
これは会社の仕事でも当てはまる法則です。
抽象度の低い自分の仕事から、抽象度の高い会社の経営戦略まで「抽象度の適応範囲」が広いほど「当事者意識が高い」と言える訳です。
- 抽象度低:日常業務
- 抽象度中:組織業務
- 抽象度高:経営戦略
当事者意識を持つことはAI、IoTなどが台頭する時代を生き残る鍵
当事者意識を持つことは超デジタル時代の現代社会だからこそ、非常に大切だと考えています。
最近流行している、AIやIoTなどには「当事者意識」という概念はありません。
決められたアルゴリズムに応じて淡々粛々と動作します。
要は当事者意識(抽象度)のレンジが固定されているということです。
逆に人間には「当事者意識」をいう概念があります。
人間は当事者意識(抽象度)のレンジは固定されていません。
完全にどこからどこまでを思考するかは個人の自由です。
これは人間がAIに仕事を奪われないための大きなヒントだと考えています。
鋭いあなたはすでにお気づきだと思いますが、当事者意識はAI、IoT全盛の超デジタル時代に人間が生き残る鍵の一つなのです。
意外な盲点ですが、超デジタルだからこそ超アナログが力を発揮するのです。
そんなアイロニーが素敵なのではないでしょうか?
当事者意識を持つためのポイント

さて、ここからは当事者意識を持つために心掛けたいことを解説していくことにしましょう。
当事者意識を持つためのポイント1:抽象度を操る
当事者意識を持つためのポイント1つ目は抽象度を操ることです。
前述した内容に近いですが、抽象度の高い目線、抽象度の低い目線、そして時代の流れなど、多角的な目線で物事を見る癖をつけることです。(いわゆる「鳥の目、虫の目、魚の目」を常に意識することです。)
是非試してみて下さい。
※この内容は別の記事でも詳しく解説していますので、興味のある方は下記リンクからご一読下さい。
当事者意識を持つポイント2:興味を持ち、仮説を立てる
当事者意識を持つためのポイント2つ目は興味を持ち、仮説を立てる癖をつけることです。
日常の様々なことを観察してみることです。
「あの店はなぜいつも行列が出来ているのか?」「この車はなぜ高いのか?」「この人はなぜ無愛想なのか?」
ふとした日常を常に観察し、自分なりの仮説を持つことです。
仕事とは関係の無いように見える「OFF」の時に興味を持ち、仮説を持っておくと、仕事で「ON」の時にふと繋がるのです。
ふと繋がり、発言したことが「鋭い意見」になることは少なくありません。
そのふとした発言で周囲から当事者意識が高いと評価される訳です。
日常でこそ、興味を持ち、仮説を立てるようにしましょう。
当事者意識を持つためのポイント3:天才の解釈に触れる
当事者意識を持つためのポイント3つ目は天才の解釈に触れることです。
これは「ポイント1:抽象度を操る」、「ポイント2:興味を持ち、仮説を立てる」前に実行したいことです。
私は典型的な凡人です。
恐らく、私が100年唸って考えても出てこない答えや視点を天才達はいとも簡単に出してきます。
天才の解釈に触れると、新たな視点を手に入れ、物事を多角的に見られるようになります。
天才達の思考を「脳へプログラミング」すると、確実に当事者意識は向上します。
天才の解釈に触れ、教養を磨きましょう。
※関連記事は以下です。
リンク:【読書ができない、苦手な人へおすすめの読書方法】人生を豊かにする本の読み方のコツ
当事者意識を持つポイント4:当事者意識を持たないポイントを決める
当事者意識を持つポイント4つ目は当事者意識を持たないポイントを決めることです。
これは非常に逆説的ですが、意外に大切なので記載します。
当事者意識は非常に大切なのですが、当事者意識を持たないポイントはきちんと決めておくことが大切です。
人生という限られた時間の中で「当事者意識の質を上げる」という発想が非常に大切だということです。
例えば、「誰か芸能人が不倫した」とか、「誰かが経歴詐称した」とか、などに当事者意識を持ってしまい、SNSでのバッシングに力を入れている人もいますが、ハッキリ申し上げて時間の無駄です。
優秀なあなたはそんな観点でも考えてみて下さい。
当事者意識を持たせるための指導法
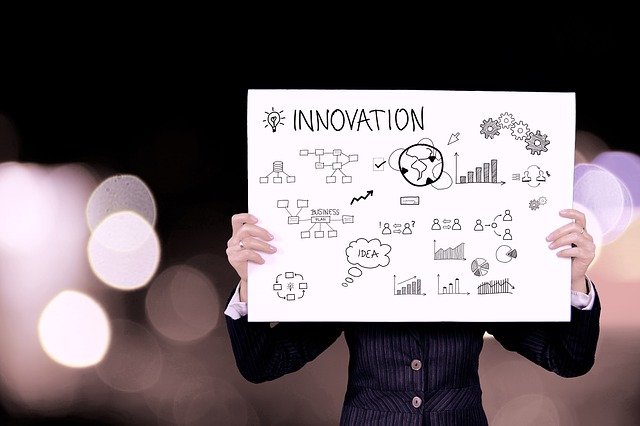
さて、ここからは「部下にもっと当事者意識を持たせたい」「当事者意識を持たせるためには何をすればいいのか?」のヒントをお伝えしていきたいと思います。
※ヒントになりそうな類似記事は以下に集約しましたので、興味のある方はご一読下さい。
リンク:【強い組織の特徴6選】自動車メーカーで学んだ強い組織の作り方
リンク:【部下・後輩指導でお悩みの方必読】指導上手な人は何が違うのか?
リンク:【2030年予想図】今後、仕事で必要とされるスキルとは?
当事者意識を持たせるためには?1→質問を投げかける
当事者意識を持たせるために心掛けたいこと1つ目は質問を投げかけることです。
何も考えていなさそうな部下にはとにかく質問を投げかけまくることです。
どんなに鈍い部下でも毎回必ず質問を投げかけられれば、多少なりとも考えるようになります。
その「考える癖付け」のきっかけを強制的に作り出すことことが当事者意識を持つことに繋がります。
「当事者意識を持て」と言って響く部下はそもそも意識が高い部下だけです。(笑)
意識の低い部下にはドラゴンクエストの呪文のように質問を投げかけることです。
何事も0→1に進歩させる時が大変なのは世の中の仕組みそのものです。
忍耐強く質問を投げかけましょう。
当事者意識を持たせるためには?2→興味のありそうな事と関連付ける
当事者意識を持たせるために心掛けたいこと2つ目は興味のありそうな事と関連付けることです。
部下の仕事での得意分野や趣味を把握し、その分野や趣味と紐付けして話すと、当事者意識が高くなりやすいです。
相手が興味のありそうなことと関連付けて話してあげるという発想は非常に大切です。
マネジメントが上手い上司や先輩は意識的にも無意識的にも必ずやっていると言っても過言ではありません。
明日から意識してみましょう。
当事者意識の醸成は組織/個人を成長させる

最後まで読んでくださった方、ありがとうございました。
本記事に記載した内容を是非、お試し頂けますと幸いです。
今回は以上です。
