こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- 管理職になったが、うまくいかない、つらいと悩んでいる人
- 管理職に必要な能力、スキルを学びたい人
- 管理職の役割について学びたい人
- 管理職はAIに仕事を奪われるのではないか?と不安を感じている人
※この記事と併せて読みたい記事
リンク:【リーダーとは何か?】現代社会のリーダーに求められるもの
リンク:【部下・後輩指導でお悩みの方必読】指導上手な人は何が違うのか?
リンク:仕事でありえないミスを連発→再発防止の仕組み化で価値を生もう
それでは、「ヨット講座」始めましょう。(※ヨットはこんな人です。Twitterフォロワー数は2020/11/20現在です。)

はじめに:「管理職」とは?

はじめに管理職とは何か?について考えていくことにしましょう。
管理職とは?→組織方針を遵守できるように管理する役割の人
会社にはCSR方針、中長期経営計画、年度方針などの様々な方針や計画があります。
様々な方針や計画で定められた理念、目的、日程、目標値などの様々な内容を管理していく人ということです。
管理職になったら、CSR方針、中長期経営計画、年度方針は頭に叩き込む!
管理職になったら、会社のCSR方針、中長期経営計画、年度方針は必ず頭に叩き込むことです。
外部リンク: Wikipedia Corporate Social Responsibility; CSR
CSR方針、中長期経営計画、年度方針を理解していない管理職は「宝探しの地図や目的地を持たないトレジャーハンター」と同義です。
会社の理念、目的、日程、目標値をきちんと自分の中に染み込ませることが大切です。
鋭い部下は意外にそんな部分を観察しています。
管理職の役割とは?
管理職の役割はシンプルに考えると3つしかありません。
- 管理職の役割1:組織方針の遵守推進
- 管理職の役割2:部下の育成
- 管理職の役割3:責任を取る
順番にご説明していきましょう。
管理職の役割1:組織方針の遵守推進
管理職の役割1つ目は組織方針の遵守推進です。
もう少しシンプルに申し上げると、「自分の管轄内を俯瞰して見る、都度修正する」ということです。
プレーヤーである一般社員はどうしても、目の前の業務を処理するので精一杯になってしまいがちです。
自分の状況を俯瞰的に見て、都度是正できるような優秀な社員は多くありません。
目的、日程、目標値等の「小さな旗」を自分の管轄内に都度立て、一般社員を導いていくことが大切です。
※スケジュール管理、時間管理が苦手な部下がいらっしゃいましたら、以下の記事を読むように指導して下さい。(笑)
リンク:【日程・スケジュール管理のコツ】管理できない人が心がけるべきポイント7選
リンク:【自動車メーカーの日程表の書き方】日程表で押さえるべきポイント3つ
リンク:【時間管理ができない・苦手な人は必読】時間管理術:3つの軸を押さえよう
管理職の役割2:部下の育成
管理職の役割2つ目は部下の育成です。
非常に逆説的な言い回しになってしまいますが、管理職が管理しなくても良い仕組みを作り上げるのが、管理職の仕事とも言えます。
そのためには部下を育成し、自発的に行動・管理する風土を作り上げる必要があります。
部下育成が非常に大変なのは重々理解していますが、最終的には自分が「楽をする」一番の近道なのです。
※強い組織の作り方、仕組み化などは別の記事で解説していますので、興味のある方はご一読下さい。
リンク:【強い組織の特徴6選】自動車メーカーで学んだ強い組織の作り方
リンク:【仕組み化の方法】自動車メーカーはなぜ強いのかを2つの軸で解説
管理職の役割3:責任を取る
管理職の役割3つ目は責任を取ることです。
社長のお給料が高いのは、何か社会的な問題を引き起こした時に責任の矢面に立つための保険料のようなものです。
部長のお給料が高いのは、自分の管轄組織が問題を引き起こした時に責任の矢面に立つための保険料のようなものです。
課長のお給料が高いのは、自分の管轄チームが問題を引き起こした時に責任の矢面に立つための保険料のようなものです。
「管理職の給料が高い」などと叫んでいる平社員などがよく居ますが、私はそうは思いません。
なぜなら、「何かが発生した時に矢面に立つ責任」に対してお給料が支払われていると思っているからです。
逆説的に考えると、何か問題が発生した際に責任を取らない管理職は必要ありません。
例え、部下が何か勝手に判断して失敗したとしても、それは管理出来ていなかったあなたの責任と考えるようにしましょう。
リンク:【成長するには?→他責思考を改善しよう!】他責思考改善のヒント
管理職の重要性

リモートワーク、AIの発達、ギグエコノミーの進展により、「管理職は不要」と叫ぶ人が増えていますが、本当にそうでしょうか?
AIに仕事を奪われない管理職の能力→イレギュラー対応能力
仕事というのはトラブルやイレギュラーがつきものです。(私自信が散々やらかして来ましたので、なおそう思います。笑)
AIというのはインプットされたアルゴリズムに応じて、「模範解答」を弾き出す能力は人間よりも遥かに優れています。
これはもはや人間には勝ち目がないでしょう。
しかし、AIが極端に苦手な能力があります。それは「引き算」や「イレギュラー/トラブル対応」です。
AIは「引き算」で物事を考えることが出来ませんし、「イレギュラー/トラブル」が発生した際には適切な解答が弾き出されません。
「模範解答」が無い状態で、いかに本質を突いた適切な状況整理や指示ができるかが管理職の能力です。
この内容を理解し、極めていけば、AIに仕事を奪われることは絶対にありません。
※AIと人間については別の記事で解説していますので、興味のある方はご一読下さい。
管理職は「信用・信頼」を管理するということ
現在はギグエコノミー全盛の時代です。
※ギグエコノミーについては別の記事で解説しています。
リンク:【ギグエコノミーの正体】これからの時代に考えたいこと
ギグエコノミーの進展に伴って、管理職の不要性が叫ばれつつあります。
それは半分合っていて、半分間違っていると思っています。
ここまでに記載した内容が出来ていない管理職は確かに淘汰されていくことでしょう。
しかし、ここまでに記載した内容がきちんと出来ている管理職は逆に需要が増えると考えています。
これは世の中の仕組みを観察してみると面白いことに気付かされます。
プラットフォーム運営会社は「ギグワーカー管理職」
ウーバー、ランサーズ、エアビーアンドビーなどのいわゆるギグエコノミーのプラットフォームを観察してみると面白い構図に気付かされます。
初対面の個人対個人のやりとりというのは「信用・信頼性」が乏しくなります。
そこで需要と供給の間に生じている「信用・信頼性」の乏しさを担保しているのが、ウーバー、ランサーズ、エアビーアンドビーなどのプラットフォーム運営会社です。
要はこの会社が担保しているなら大丈夫だろうという「信用・信頼性」を買ってくれる訳です。ギグワーカー管理職と言っても良いでしょう。
古くから商社などが個人事業主を取りまとめていた構図が、個人レベルにも該当するようになってきているのです。
ここまでに記載してきた内容がきちんと出来ている管理職の方は、これからますます需要が増えることでしょう。
ギグで個人化が進むからこそ、重要な案件や難易度が高い案件では逆に管理職、管理できる人の需要が増えるのです。
管理職 あるべき姿:必要な能力、スキル 5選
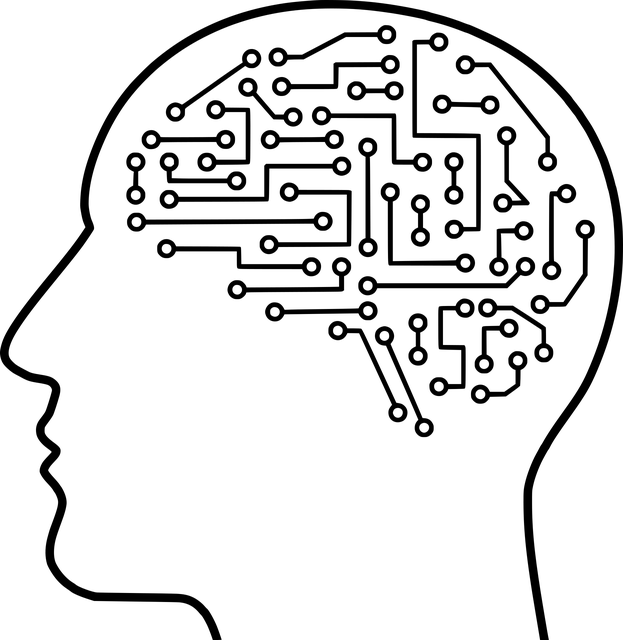
ここからは管理職のあるべき姿、必要な能力、スキルを考えていきましょう。
管理職に必要な能力1:本質を見抜く力
管理職に必要な能力1つ目は本質を見抜く力です。
そのような仕組みを構築しようと考えると、必ず本質を押さえる必要が発生します。
なぜなら本質を押さえると応用性、再現性、拡張性などが非常に高いからです。
管理職は単発的な管理ではなく、常にその他分野に応用できる内容は無いか?、次回の案件で再現するには?などを考え続けなくてはなりません。
そのためにも本質を見抜く意識を持つことが大切なのです。
※本質を見抜く思考法は別の記事で解説していますので、ご一読下さい。
管理職に必要な能力2:会社と社員のインターフェースになる力
管理職に必要な能力2つ目は会社と社員のインターフェースになる力です。
現代社会は価値観の多様化が進んでいます。
同じ年に入社した新入社員でも、入社した「目的」、業務をこなす上での「目標」などは全く異なると言っても過言ではありません。
そして、転職のプラットフォームなども発達していますので、「会社の目的、目標」と「個人の目的、目標」に大きな乖離があると、転職、退職という選択肢を取る社員の方も少なくないです。
実際に大きな乖離がある場合は止める必要はありません。
ポイントは普段から話を聞く姿勢を明確に打ち出し、よく会話しておくことです。
例えば、仕事よりも家庭を重視したいという部下とは、定時に帰れるようにするための効率化について話合ってみるのもいいでしょう。
きちんと意味付けを与えると、モチベーションが向上し、爆発的に成長していく部下というのは意外に多いです。
インターフェースになることを心がけましょう。
管理職に必要な能力3:整理整頓する力
管理職に必要な能力3つ目は整理整頓する力です。
仕事とは何でしょうか?私は思考を究極まで整理整頓することだと答えます。
これを管理職に当てはめて考えてみると、組織を整理整頓するということになります。
翻って考えてみましょう。
あなたの会社の机の上は整理整頓されているでしょうか?パソコンのデスクトップにアイコンが散乱していないでしょうか?
もし机の上に書類が散乱していたり、パソコンのデスクトップにアイコンが散乱しているならば、まずはそこから整理整頓しましょう。
私が自動車メーカーに勤務していた頃の部長の机とパソコンのデスクトップは感動するほどに綺麗でした。そして、頭の回転が異常に早く、決断が速く、出世街道まっしぐらの方でした。
退職した今でも尊敬しています。
少し厳しいことを申し上げると、見える部分すら整理整頓出来ない人が思考や仕組みを整理整頓できるはずがないのです。
ヒヤリとした人は整理整頓を今すぐ始めましょう。
※整理整頓は別の記事で解説していますので、ヒヤリとした人はご一読下さい。
リンク:【整理整頓力】家庭、仕事で能力を発揮する人の6つの考え方
管理職に必要な能力4:教養
管理職に必要な能力4つ目は教養です。
私が考える教養とは「物事が多角的に見られること」「時間軸、空間軸での学びの深さ」だと考えています。
現代社会は日々新しいビジネスモデルが生まれていますが、大体は歴史のオマージュのようなものが繰り返されています。
時間軸、空間軸での学びが深いと、「このビジネスモデルはこの歴史のオマージュだな」とか、「次はこんなビジネスモデルが流行するのかな?」といったことが想像できるようになります。
時代の流れや状況を察知するには教養が不可欠なのです。
また、管理職になると社外の役職者と交流を持つことも増えます。
会社や業界が違う人といきなり会ってお話する場合には「相手との共通言語」を素早く発見しなくてはなりません。
「相手との共通言語」を素早く見出して、会話の水準をチューニングできるのが教養ということです。
教養の大切さ、ご理解頂けましたでしょうか?
参考:管理職が読むべき本
管理職が読むべき本は以下の記事にまとめてありますので、参考にしてみて下さい。
管理職に必要な能力5:判断・決断する力
管理職に必要な能力5つ目は決断する力です。
「うーん、どうしよう」とひたすら迷うタイプの管理職の下につくと、部下は困ってしまいます。
間違ってもいいから素早く判断・決断することです。どのみち責任を取るのは自分なのですから間違ってもいいのです。
判断・決断が遅い上に間違った場合などは目も当てられません。
全てがリアルタイム化し、高速化している社会では判断・決断に迷っている時間などありません。
1秒で見える景色がまるで変わる状況になることがあることを知りましょう。
※決断力は別の記事で解説していますので、ご一読下さい。
リンク:【決断力は人生を豊かにする】決断できない人に贈りたい言葉
管理職はやりがいでやる仕事

最後まで読んでくださった方、ありがとうございました。
管理職は大変な仕事です。正直割に合わないと思うこともあるでしょう。
真面目で勉強熱心なあなたの今まで以上のご活躍をお祈りしております。
今回は以上です。
