こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- 質問が苦手、できない人
- 質問の仕方、コツを学びたい人
- 質問が上手になりたい人
※この記事と併せて読みたい記事
内部リンク:【理解力を高める方法→型の理解】理解力がない人→高い人へ
内部リンク:【カモられる人の特徴 5選】カモにされるのを避ける方法
それでは「ヨット講座」始めましょう。
※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/1/25現在です。)

質問の考え方

まずは質問とは何かについて考えていきましょう。
当たり前のように使われている「質問」という言葉。
この「質問」という概念に対して真剣に考えたことがある方はどれくらいいるでしょうか?
「質問」という概念について、真剣に考えてみると、様々な興味深い事実に気付かされます。
良い機会ですので、一緒に考えていきましょう。
質問とは?→不明点について問いただすこと
まずは模範解答から始めましょう。
質問とは「不明点について問いただすこと」です。
わからないところ、疑わしい点について問いただすことを指します。
この前提条件を基に深掘りして考えていくと、様々な面白い事実に気付かされます。
質問の考え方1→目的ではなく、手段である
まずは質問の考え方において、非常に重要なポイントからいきましょう。
最近はSNSなどの発達もあり、「質問」が手段から目的に成り代わっている人をよく見かけます。
目的を持った質問のふりをして、著名人に絡んで、返信が来ると喜んでいるタイプの人です。
少し厳しい申し上げ方をします。
このタイプの人は質問すること自体が「目的」になっている一番ダメな典型例です。
質問の目的・意図を明確にして質問をする
例えば、あなたが飲食店を経営していると仮定して、抽象的な例え話で考えてみましょう。
あなたがコンサルに「利益率ってどれくらいがベストですかね?」と質問したとしましょう。
この質問は非常に困る質問です。
コンサル側としては、利益率が低いから悩んでいるのか、利益率が高いから素材のコストを上げてお客様に還元しようとしているのか、はたまた利益額を増やしたい意図からの質問なのかが読み取れません。
この例え話の質問の模範解答例を提示すると、「現状利益率が25%と想定以上に高収益です。素材グレードをUPしてお客様に還元したいのですが、利益率をどのあたりに設定するのがベストでしょうか?」となります。
このように質問の目的・意図を明確にして質問することが大切です。
質問の考え方2→やるために質問する、やらない言い訳に使わない
質問で重要な考え方2つ目は「やるために質問する」ということです。
質問をする人の中には、何回も何十回も質問をして、実行を先延ばしにしようとするタイプの人がいます。
これはダメな質問の典型です。
やらない言い訳に質問を使わないことです。
意外にも、無意識で「やりたくない質問」をする人は多いので、自分がそうなっていないかを虚心坦懐に見直しましょう。
「やりたくない質問」を連発して、上司に嫌われた人を大企業に勤務していたサラリーマン時代に何人も見ています。
もちろん干されていました。
質問の考え方3→質問力はそのままスキルであり、能力の集大成
質問で重要な考え方3つ目は「質問力はそのままスキルであり、能力の集大成」ということです。
なぜなら、質問にはその人が普段どれだけ勉強しているかが顕著に顕在化するからです。
物事の捉え方、視野の広さ、思考の型の成熟度、本質を捉える力、相手への伝え方、語彙力などが全て顕在化するのが「質問」です。
もうお分かりでしょうが、「質問力」はそのまま能力であり、スキルなのです。
余談:質問力はAI時代に生き残る武器
AIには「疑問」「質問」という概念はありません。
与えられたアルゴリズム以外では「疑問」は浮かびませんし、「質問」という概念はありません。
「疑問」、「質問」という概念があったからこそ、人間はここまで進化して来られたのだと思います。
この記事を検索して見て下さっている方はそのようなことに気づいたセンスの良い人だと思います。
AIに負けないように質問力を鍛えましょう。
内部リンク:【2030年予想図】今後、仕事で必要とされるスキルとは?
質問が苦手、できない人に伝えたい質問の仕方 4つのコツ

ここからは「質問が苦手」「質問が上手くできない」という人に伝えたい質問の仕方のコツをまとめていきます。
基本的な部分から応用的な話まで順番にみっちり解説していきます。
質問の仕方のコツ1:5W1Hで物事の全体像を捉える力を磨く
質問の仕方のコツ1つ目は5W1Hで物事の全体像を捉える力を磨くことです。
質問が苦手、できないという人に見られる傾向としては、質問以前に問題が潜んでいる場合が多々あります。
質問というのは、「不明点について問いただすこと」だと先述しましたが、「何が不明点なのかが、不明点」のような状態になっている人も少なくありません。
少しキツい申し上げ方をするならば、質問をする前の土台・基礎がグラグラな状態です。
質問を考える前に5W1Hで物事の全体像を整理整頓する
良い質問、鋭い質問をするには、5W1Hで物事の全体像を整理整頓することが不可欠です。
要は企画や計画の全体像について自分自身の中で正しく理解できていることが不可欠だということです。
※企画立案5つのステップとは?と問われてパッと出てこなかった方は下記の記事をご一読頂けますと幸いです。
「目的は何か?」「ニーズ志向/シーズ志向の前提条件」「予算/日程感(5W1H)」「企画のポイント」「実行計画案」などをきちんと理解しているか否かで、頭の中に浮かんでくる質問の質は全く変わるのです。
内部リンク:【整理整頓が苦手、できない人は必読】家庭、仕事での整理整頓のコツ
内部リンク:【現代の必須スキル→情報5S、整理整頓】錯綜する情報のまとめ方
質問の仕方のコツ2:思考の型に当てはめて考える
質問の仕方のコツ2つ目は思考の型に当てはめて考えることです。
質問というのは相手のお時間(=命)を頂く行為です。
内部リンク:【期限遵守・厳守は人生の本質】期限を守れない人が意識すること
「仕事だから質問に答えて当然」「上司なんだから、質問に答える義務がある」などと考えてはいけません。(説明の仕方がイマイチなケースもあるかとは思いますが、一旦ここでは除外します。)
そこで大切になるのは、思考の型に当てはめて、自分なりに深掘りして考えてみることです。
内部リンク:【思考力を鍛える4つの型】AIに負けない思考方法、思考の型
「わからないことの共通点をまとめる」→本質的に理解できていないことは何かを考える。
「多角的に考える」→物事を正面ではなく、斜めから見て考える。わからないことを多角的に考え、わからない全体像を描く。
「歴史から学ぶ」→会社の資料などを見直し、自分の質問したい内容についての答えが書いていないか探す。→もし無ければ、質問に答えて頂いた後に自分がマニュアル化することを検討する。
このように自分の頭で考えた上で、初めて質問に移行することです。
このようなプロセスを経由しているか否かで質問の質は全く変わります。
これを日々意識するようにしましょう。
質問の仕方のコツ3:自分の解釈を伝える
質問の仕方のコツ3つ目は自分の解釈を伝えることです。
質問の仕方のコツ1、2を経由して初めて具体的な質問に移行します。
ここで大切になるのが、「自分の解釈を伝える」ことです。
質問の仕方は大きく分類すると2種類に別れます。
「〇〇が分からないです。」という受動的な質問の仕方。
「〇〇と解釈したのですが、その認識で合っておりますでしょうか?」という能動的な質問の仕方。
例えば、全体会議後の上司に対する質問で考えてみましょう。
Aさんは「次回の会議までに準備しておくものはありますか?」と質問します。
Bさんは「うちの部署の宿題は〇〇だと判断しました。宿題には挙がりませんでしたが、〇〇の資料が宿題ならば、××の資料も併せて用意した方がよろしいかと思ったのですが、いかが致しましょう?」と質問します。
もちろん、何が分からないか分からない状態では、Aさんの質問をするしかありませんが、極力Bさんのような質問をすることを常に意識してみましょう。
質問の仕方のコツ4:質問後はすぐやり、具体的な質問に繋げる
質問の仕方のコツ4つ目は質問後はすぐやり、具体的な質問に繋げることです。
よくいるのですが、質問ばかりして、行動を起こさないタイプの人にならないように注意して下さい。
やれば、10秒で分かるようなことを永遠と質問するタイプの人です。
質問される側としては、やれば10秒で分かるような質問をされるとうんざりして二度と質問に答えて貰えなくなります。
質問する相手とのパワーバランスによっては、下手すると永久追放される可能性すらあります。
これが社会の仕組みの現実です。
質問に答えて頂いたら、すぐに行動する。
これを心に刻みましょう。
そして、実際に行動したことで顕在化した具体的な不明点を先述したような内容で質問する。
これを繰り返すことにより、質問力が向上するのです。
質問力を鍛える日常生活のコツ
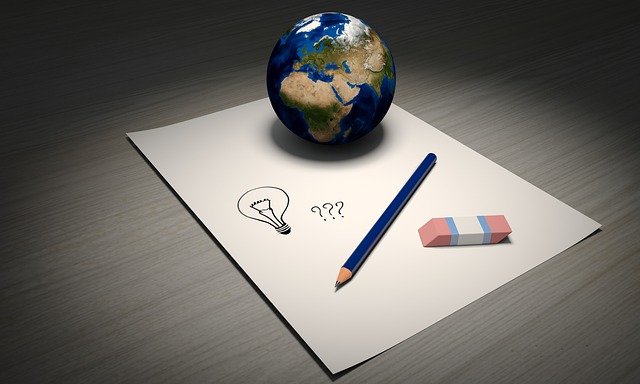
最後にオマケです。
質問力を鍛える日常生活のコツがいくつかありますので、ご紹介しておきます。
質問力を鍛える日常生活のコツ1:日常を切り取る
質問力を鍛える日常生活のコツ1つ目は日常を切り取ることです。
日々の何気ないことに興味を持って観察している人とそうでない人とでは質問力がまるで異なります。
何かを疑問に思って質問できるか否かは、日常から何を感じ取り、切り取り、インプットしているかが非常に影響しています。
様々なことに気づき、日常を切り取る意識を持つことが重要です。
内部リンク:【気づく力は能力の集大成】気づく力を鍛えるトレーニング 5選
質問力を鍛える日常生活のコツ2:本を読む
質問力を鍛える日常生活のコツ2つ目は本を読むことです。
ビジネス書、哲学書、小説など全てに言えることですが、本を読むことにはメリットしかありません。(強いてデメリットを挙げるのならば、妻を放置して、マジギレされるリスクがあることくらいでしょうか。笑)
語彙力がUP、想像・創造力がUP、他者目線が身につくなどなど、メリットしかありません。
本を読みましょう。
内部リンク:【読書ができない、苦手な人へ】人生を豊かにする本の読み方のコツ
内部リンク:【隠れた名著】おすすめの名著リスト 教養が身につく14冊
内部リンク:【本の楽しみ方】人生を変えるおすすめの本の楽しみ方 5選
内部リンク:【小説の楽しみ方】人生を変える小説の楽しみ方 5選
今回は以上です。
