こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- 仕事、化粧、ファッションなどでの上達の近道を模索している人
- 真似する場合のポイントを学びたい人
- 真似されるのがストレスだという人
※この記事と併せて読みたい記事
内部リンク:インプットが苦手な人へ送る3つの方法・コツ→ポイントは全体像
それでは「ヨット講座」始めましょう。
※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/3/4現在です。)

真似とは何か?
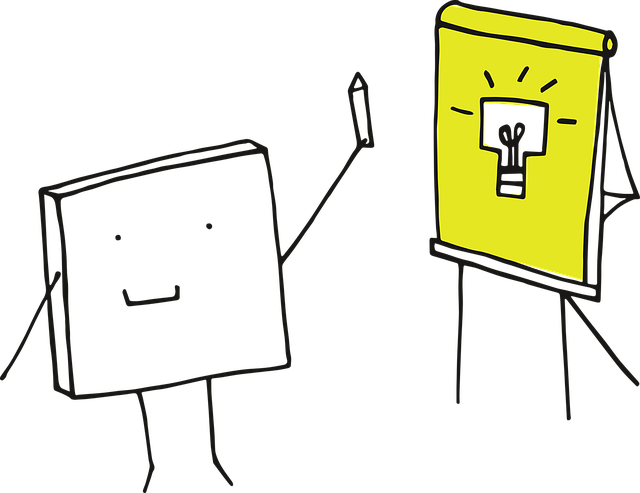
まずはじめに「真似とは何か?」について考えていきましょう。
真似とは何かを考えていくと面白い事実に気づかされるからです。
真似とは何か→形だけ似た動作をすること
まずは模範解答からいきましょう。
まねること。また、形だけ似た動作をすること。模倣。「ボールを投げる真似をする」「アメリカ映画の真似をする」
出典:Goo辞書
真似をすること→型をマスターすること
真似の模範解答が「形だけ似た動作をすること」であることは先述しました。
陸上選手が走るフォームには基本の型があります。
サッカー選手がボールを蹴るフォームには基本の型があります。
仕事の進め方には基本の型があります。
化粧の仕方には基本の型があります。
どんな分野にも必ずベースとなっている基本の「型」があるのです。
基本の型を理解し、「形だけ似た動作をすること」を実行することが真似ということです。
内部リンク:【理解力を高める方法→型の理解】理解力がない人→高い人へ
人間は真似をすることにより発展してきた
古い時代の人間の移動手段は「馬」でした。
人間以上に高速で長距離を走れるのが「馬」だったからです。
「馬」の特性を真似し、更に発展させたのが馬車です。
更に馬車のスピードや快適性を真似しながらも、質的変化を起こしたのが自動車です。
自動車のパワーが「馬力」と語られるのはそのような所以からなのです。
更には船や潜水艦は魚の特性を真似したものです。
飛行機は鳥の特性を真似したものです。
我々人類が発展できた理由は「真似」にあるのではないでしょうか。
AIには「真似する」という概念は無い
最近流行しているAIなどには「真似する」という概念はありません。
内部リンク:【AI vs 人間】人間にしかできないことを仕事にしよう!
「コード・画像をコピー」することはできますが、「真似する」ことは出来ないのです。
そして、人間のように「真似する」ことを起点に質的変化を起こすことは出来ません。
内部リンク:変化する時代を生き残る人材→結論:想像/創造人材が時代を作る
そんな観点で真似することを考えてみると、新たな発見があるはずです。
上達するには真似すること

仕事、化粧、ファッション、スポーツなど何でもそうですが、上達するにはまずは真似から入ることです。
なぜ、上達をするには真似から入るのが良いのか?
その理由を解説していきます。
前提条件:人間には「期限」があるから真似をするべき
「上達するにはまずは真似から入ること」この主張は先述させて頂きました。
この主張の根底にある前提条件があります。
それは「人間の命には期限がある」からです。
内部リンク:【期限遵守・厳守は人生の本質】期限を守れない人が意識すること
我々人間の生命はせいぜい100年です。
この100年の期限の中で何ができるかを考えるのが人生です。
人類の歴史というのは西暦だけで2021年あります。
古今東西の天才達が脈々と真似をし、質的変化を起こしました。
起業家などが更にそれを真似し、質的変化を起こしました。
人間の真似の系譜と質的変化の結晶が現在の我々の生活な訳です。
それをたった100年で一から考えるのは、超天才でもまず無理でしょう。
だからこそ、模範解答を「真似すること」で時間を節約することが大切になる訳です。
現状の模範解答は「真似すること」でマスターし、それを組み合わせて新たな質的変化を目指す。
上達が早い真似の仕方:本質・要点を押さえる
真似の良いところは、すでに実例があるということにつきます。
真似をしないと全て自分で考え、実行し、結果分析をしなくてはなりません。
しかし、真似をする場合、この時間が大幅に削減出来ます。
現在、本質的に上手くいっているモデルケースを観察、分析し、自分で実行しながらモデルケースとの差異を分析することができるからです。
素早く上達するためには「真似するべき本質・要点は何か?」を考えてみて下さい。
内部リンク:【人生・仕事で大切なこと→要点をおさえる】要点をまとめる方法
一定レベルまで上達したら、真似したことを組み合わせる
本質・要点を押さえ、ある程度まで上達したら、真似したことを自分の感性で組み合わせてみましょう。
真似した模範解答を踏み台にして、自分の感性で組み合わせることによって、真似からオリジナルに変化します。
真似する時は必ずこれを意識して真似るようにすると、上達がなお早いのです。
真似をする際のポイント→真似する人を間違えない
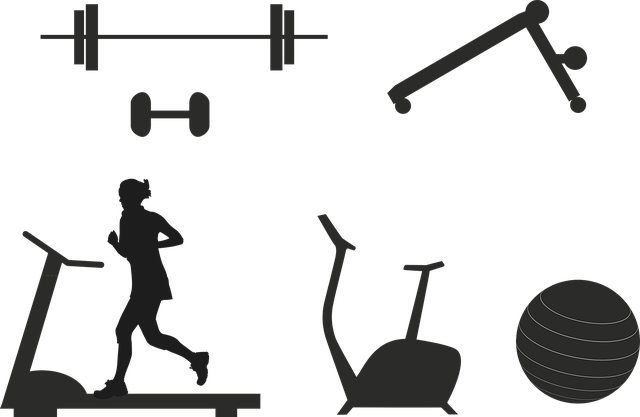
真似をする際に絶対に外してはならないポイントがあります。
それは真似する人を間違えないことです。
一番分かりやすい例がTwitterです。
怪しいカリスマがうじゃうじゃいます。(笑)私のTwitterミュートリストは余裕で3桁を超えています。
資本主義社会で搾取されないためには、自分の頭で「誰を真似するべきなのか?」を考えなくてはなりません。
内部リンク:搾取されない生き方をする方法5選:資本主義の仕組みを理解する
真似するべき人とは?→「経歴を見て決める」
真似するべき人、学ぶべき人とはどんな人でしょうか?
私は「経歴を見て決める」を徹底しています。
具体的なヒントは下記の名著リストの「著者の経歴」にあります。
「著者の経歴」を調べてみて下さい。真に学ぶべき人が分かるはずです。
内部リンク:【隠れた名著】おすすめの名著リスト 教養が身につく14冊
おわりに:真似されることがストレスだという人へ
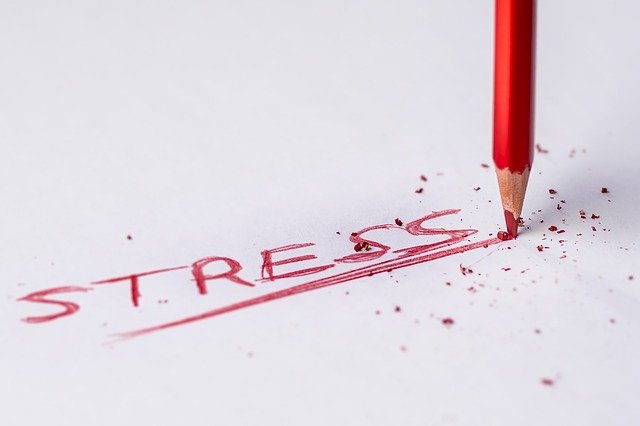
おわりに、真似されることがストレスだという人へのメッセージです。
もしかしたらあなたは真似されることにストレスを感じている方かもしれません。
なぜなら、「他者との差異」で自分の価値を見出していると言えるからです。
自分に自信のある人は真似されようが、パクられようが特に気にしていません。(著作権の侵害のような自分に経済的被害が及ぶものは除きます。)
真似されたら、「真似されて、パクられてナンボだな」と思っているくらいでちょうど良いのです。
そんな心の余裕や視野の広さがあることが、「真の自信」なのではないでしょうか?
内部リンク:【視野を広げると生き方の可能性が広がる】視野が広い人の考え方
今回は以上です。
