こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- 知的好奇心を高めるメリットを知りたい人
- お子さんに知的好奇心を高めて欲しいと思っているご両親
- 大人/子供問わず好奇心を高める方法を学びたい人
※この記事と併せて読みたい記事
内部リンク:仕事がつまらないと感じたら→自分で面白くする工夫をしよう!
内部リンク:【子育て・教育方針の考え方 5選】子供が成長する教育法
内部リンク:学校教育の問題点→AIのように模範解答しか教えないこと
内部リンク:感性を磨く方法7選→子供・大人共に感性を育むと大きな武器に!
それでは「ヨット講座」始めましょう。
※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/3/5現在です。)

知的好奇心とは何か?
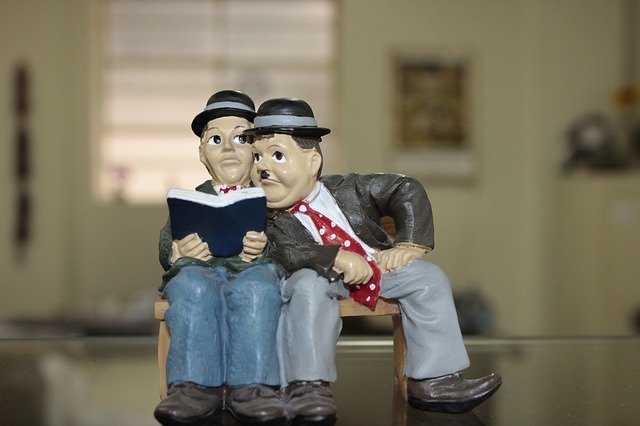
まずは「知的好奇心とは何か?」について考えていきましょう。
まずは模範解答からいきましょう。
知的好奇心とは?→物事を探求しようとする根源的な心
好奇心(こうきしん)とは、物事を探求しようとする根源的な心。
自発的な調査・学習や物事の本質を研究するといった知的活動の根源となる感情を言う。
出典:Wikipedia
知的好奇心とは何かの模範解答は上記になります。
さて、ここからは模範解答から少し離れて考えていきましょう。
知的好奇心とは?→人間が人間たる所以
「好奇心」は動物にも存在します。
本能レベルで周囲の状況や物に好奇心を抱くことはあります。
しかし、「知的好奇心」は動物にも、AIにも、ロボットにも、昆虫にも、植物にも存在しません。
何かを知的に探求して、言語化し、「概念」にできるのはこの宇宙上で人間のみです。
知的好奇心は人間が人間たる所以なのです。
AIは与えられたデータや前提条件からしか答えを導き出せません。
しかし、人間の知的好奇心の範囲は無限です。
人間は「感覚」もあるので「データが無い」部分すら守備範囲です。
知的好奇心を持って、探求し、「模範解答」を超える。
それが可能なのが我々人間です。
AIの発展で「知的好奇心」は不要になる?いいえ、逆です。
AIの発展で人間は二局化します。
「知的好奇心を持って、AIを使う人間」と「知的好奇心を持たず、AIに使われる人間」です。
知的好奇心を持つことはAI時代を生き残るための武器なのです。
内部リンク:【AI vs 人間】人間にしかできないことを仕事にしよう!
知的好奇心とは?→人生を最高に楽しむ手段
私は知的好奇心は人生を最高に楽しむ手段であると考えています。
古今東西を観察していると面白い法則に気づきます。
歴史上でも現代社会でも「性」「食」「物」などの「肉体的快楽」をとことん追求した人は何らかの形で身を滅ぼしている可能性が非常に高いです。
逆に知的快楽を求め続けると何らかの形で飛躍している人が多いことに気づかされます。(当然、天才がゆえに、自殺した天才などの例外はいます。)
肉体的快楽は限界があります。したがって有限です。
知的快楽は死なない限り限界がありません。したがって無限です。
これを読んだあなたが、どちらの快楽を追求するかは当然自由です。
知的好奇心を高めるメリット
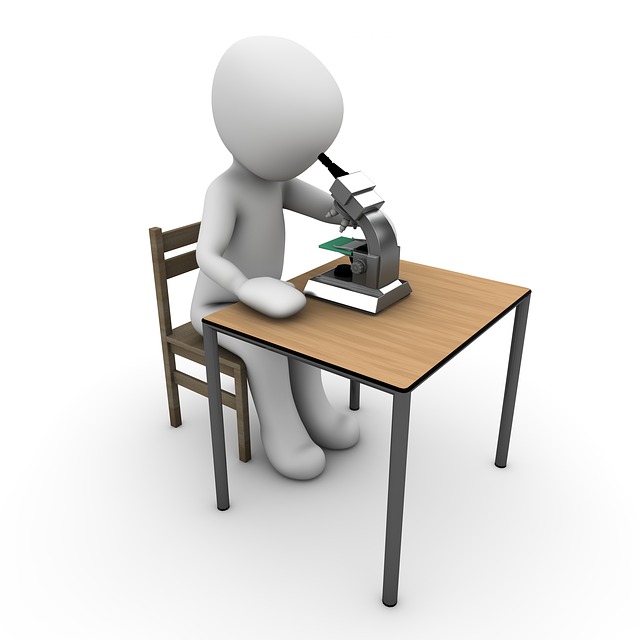
この章では知的好奇心を高めるメリットについて考えていきましょう。
本質的なものに絞って考えてみましょう。
知的好奇心を高めるメリット1:自分の頭で考える癖がつく
知的好奇心を高めるメリット1つ目は自分の頭で考える癖がつくことです。
興味を持って調べる、自分の頭で考える。
これは資本主義社会で生きる上では非常に大切なことです。
少し過激な表現であれば申し訳ないのですが、資本主義社会に生きる人を2種類に分けるとこうなります。
「①自分の頭で考え、搾取する仕組みを考える人(もしくは搾取をされない仕組みを考える人)」「②自分の頭で考えず、搾取される人」
これがありのままの現実です。
内部リンク:搾取されない生き方をする方法5選:資本主義の仕組みを理解する
知的好奇心を高めるメリット2:周囲に知的好奇心が高い人が集まる
知的好奇心を高めるメリット2つ目は周囲に知的好奇心が高い人が集まることです。
人生には面白い法則があります。
それは自分と同質性が高い人が周囲に集まるという法則です。
エリートの周囲にはエリートが集まります。
ヤンキーの周囲にはヤンキーが集まります。
愚痴の多い人の周囲には愚痴が多い人が集まります。
読書が好きな人の周囲には読書の好きな人が集まります。
あなたの周囲を観察してみて下さい。99%以上例外無くそうなっています。
これは知的好奇心も全く同じお話です。
知的好奇心の高い人の周囲には知的好奇心が高い人が集まります。
知的好奇心が低い人の周囲には知的好奇心の低い人が集まります。
永遠と愚痴・悪口・ゴシップに精を出して、生産性の無い会話を繰り返しています。
知的好奇心を持つことで「同志」が周囲に集まり、成長できるのです。
これは長いスパンで考えると非常に大きなメリットだと言えます。
知的好奇心を高めるメリット3:本質が見えてくる
知的好奇心を高めるメリット3つ目は本質が見えてくることです。
サッカーの名言を例に出して考えてみましょう。
知的好奇心を持つと、「本質は何か?」という着眼点で物事を見られるようになります。
人生は有限で限りがあります。
だからこそ、本質に最短で近づくと、相対的に人生が伸びるのです。
そんな副次作用があるのが知的好奇心を高めるメリットです。
知的好奇心を高める方法 3選

最後に知的好奇心を高める方法について3つ紹介していきます。
定番でありきたりなものから独特なものまでご紹介しますので、肌感覚に合ったものをお試し頂ければ幸いです。
知的好奇心を高める方法1:本を読む・読書
知的好奇心を高める方法1つ目は本を読む・読書をすることです。
これは模範解答中の模範解答なのですが、やはり読書は知的好奇心をくすぐられます。
特に哲学などは「絶対の答え」がありません。
古今東西の天才達と本を通じて会話し、コテンパンにやっつけられ、必死に自分なりに考える。
終わりの無い知的探求ができるのが、読書の魅力であり、哲学の魅力です。
内部リンク:【隠れた名著】おすすめの名著リスト 教養が身につく14冊
知的好奇心を高める方法2:疑問視する
知的好奇心を高める方法2つ目は疑問視することです。
知的好奇心の高い人の共通点があります。
それは何かと疑問視することです。
「この人はなぜこの発言をするのか?」
「この会社の収益モデルは何か?」
「なぜこの製品は売れているのか?」
「日常を切り取る力」「気づく力」が優れているとも言えるでしょう。
内部リンク:疑問視する力→社会を生き抜く武器:疑問を持つトレーニング方法
内部リンク:【気づく力は能力の集大成】気づく力を鍛えるトレーニング 5選
お子さんがいらっしゃる方は「なぜそう思うのか?」を会話の中で引き出すと良いでしょう。(※叱るときは「なぜ」は使わないこと。)
知的好奇心を高める方法3:囲碁・将棋
知的好奇心を高める方法3つ目は囲碁・将棋です。
これは私の独断と偏見と自己肯定ですので、話半分に聞いて下さい。(笑)
囲碁や将棋というのはハマる人にとっては非常に知的好奇心がくすぐられる遊びです。
私は小学生の頃に囲碁・将棋に凄く熱中した時期がありました。
特に将棋は「型」の研究、布石の打ち方、相手の心理など様々な角度から勉強した記憶があります。
お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、将棋の本質的な部分は仕事やスポーツ、国防などの分野でも応用可能です。
今回は以上です。
