こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- 自分の可能性を広げたいと考えている人
- 先入観にとらわれると、可能性を狭める原因になる理由を知りたい人
- 先入観を無くす方法を知りたい人
※この記事と併せて読みたい記事
内部リンク:【現状打破したい人必読】仕事や人生で現状打破をする工夫 9選
内部リンク:【0から1を生み出す人が仕事のできる人】0から1をつくる方法
内部リンク:生きる術がないという人へ→結論:固定観念を一度全て捨てる
内部リンク:安定した仕事・企業探しより大切なこと→自分の実力を安定させる
内部リンク:【カモられる人の特徴 5選】カモにされるのを避ける方法
それでは「ヨット講座」始めましょう。
※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/3/19現在です。)

先入観とは何か?
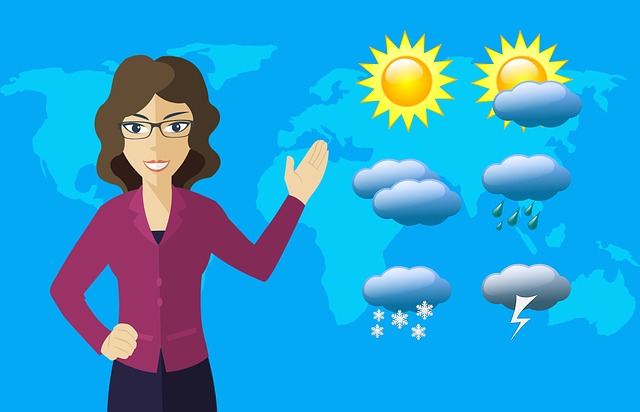
まずは先入観とは何かについておさらいしていきましょう。
先入観とは?→自分の固定観念によって自由な思考が妨げられること
前もっていだいている固定的な観念。それによって自由な思考が妨げられる場合にいう。先入見。先入主。「先入観にとらわれる」
出典:goo辞書
極論ですが、「カラス=黒色」、「白鳥=白色」、「トマト=赤色」と言ったら、おそらく誰も違和感を感じないことでしょう。
これが固定観念です。
例えば、あなたがレストランを経営しているとしましょう。
お客様から「今日のコースは赤色の野菜は使用しないで欲しい」と言われた時に、あなたはどうするでしょうか?
先入観にとらわれている場合、「トマト」は使用する食材から外してしまうことでしょう。
しかし、世の中にはよくよく調べると「白いトマト」も存在します。
この例は極論ですが、我々は日常的に先入観によって「可能性を狭めている」ことが少なくないのです。
先入観とは?→目線の偏り
少し模範解答から離れて考えてみると、先入観とは「目線の偏り」であることに気づかされます。
ある一定方向からしか物事・事象を確認せずに「それが正しい」と思い込むと、それが固定観念として積み重なっていきます。
これが目線の偏りです。
物事・事象は見る目線によって、見える光景が全く変わることが珍しくありません。
表側、裏側、斜め側など、それぞれの角度から見える景色は全く違います。
自分の目線は偏っていないか?
時々客観視してみましょう。
内部リンク:【思考力を鍛える4つの型】AIに負けない思考方法、思考の型
先入観にとらわれると可能性を狭める

先入観とは「自分の固定観念によって自由な思考が妨げられること」、そして、「目線の偏り」であるということは先述しました。
ここからは先入観にとらわれると可能性を狭める理由を解説していきます。
先入観が強い=視野が狭い=可能性が狭まる
これが可能性が狭まるメカニズムです。
目線の偏りが激しいと当然、視野が狭くなります。
視野が狭くなればなるほど、様々なチャンスや気づきを見落とすことになります。
結果的に可能性が狭まるという構図です。
内部リンク:【視野を広げると生き方の可能性が広がる】視野が広い人の考え方
先入観が強い=仕事でのリスク管理が甘くなる
先入観が強いということは「目線の偏り」だということは度々お伝えしています。
仕事などで先入観を強く持っている内容というのは実はかなり危険です。
先入観があればあるほど、物事の裏側やワーストケース、イレギュラー時の対応などが想像できておらず、何かが発生した時に大トラブルになります。
これを数回繰り返すと、出世、キャリアプランなどの可能性が狭まるリスクが上がります。
余談:先入観が強い=詐欺被害に合うリスクが上がる
余談ですが、「先入観が強い=詐欺被害に合うリスクが上がる」とも言えます。
詐欺の本質はアンカリングを打ちつけ、相手に先入観を持たせることです。
相手に先入観を持たせた上で、何らかの非合法的搾取を試みてくる訳です。
この記事を読んで勉強しているような優秀なあなたはもうお分かりでしょうが、「先入観」は百害あって一利なしなのです。
先入観にとらわれるのを防止する方法

さて、ここからは「先入観にとらわれる」のを防止する方法を解説していきます。
ご自身に合いそうなものがあれば、お試し下さい。
先入観にとらわれるのを防止する方法1:疑問視する癖をつける
先入観にとらわれるのを防止する方法1つ目は疑問視する癖をつけることです。
内部リンク:疑問視する力→社会を生き抜く武器:疑問を持つトレーニング方法
日常生活、人の発言、ネットの情報、そして自分の考え。
全てに対して疑問視する癖をつけることです。
時には前提条件すら疑問視して自分で様々な角度から考えることです。
先入観にとらわれるのを防止する方法2:本質は何かを考える
先入観にとらわれるのを防止する方法2つ目は本質は何かを考えることです。
「共通点をまとめる」「抽象度が高い部分から考える」「多角的に考える」「歴史から学ぶ」「自然から学ぶ」「長く続くこと、もの、会社から学ぶ」
これらの方法を用いて、様々な物事・事象の本質は何かを考えてみることです。
具体⇄抽象の変換を繰り返すと、先入観に囚われにくくなるのです。
先入観にとらわれるのを防止する方法3:哲学を学ぶ
先入観にとらわれるのを防止する方法3つ目は哲学を学ぶことです。
内部リンク:哲学を学ぶ意味→答えがないことを考える力を養うということ
哲学を学ぶと気づかされることがあります。
それは古今東西の哲学者達はとにかく「前提条件・定義を疑う」ことです。
この例が分かりやすい概念がジャック・デリダという哲学者が提唱した「脱構築」という概念です。
「天使と悪魔」「善と悪」のような二項対立の枠組みの矛盾を明らかにし、枠組みを取り払った上で、新たな枠組みを構築するのが「脱構築」です。
これは仕事などにも非常に役立ちます。
このような考えるヒントがゴロゴロ落ちているのが哲学です。
哲学を学んでみてはいかがでしょうか?
内部リンク:【隠れた名著】おすすめの名著リスト 教養が身につく14冊
今回は以上です。
