こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- 感情の起伏が激しいと悩んでいる人
- 感情を抑えられない、抑制できないと悩んでいる人
- 感情の制御ができないと悩んでいる人
- AIやロボットには無い感情の強みを理解したい人
※この記事の関連記事は以下です。
内部リンク:【視野を広げると生き方の可能性が広がる】視野が広い人の考え方
それでは「ヨット講座」始めましょう。
※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/1/4現在です。)

感情の抑制ができない=才能そのもの

そして、それらを様々な形で言語化することにより、現代社会を生きていく大きな武器になると考えています。
内部リンク:【2030年予想図】今後、仕事で必要とされるスキルとは?
私がなぜそう思うのか?
順番に説明していきましょう。
感情→物、対象、事象などに対して抱く気持ち
喜怒哀楽、驚き、嫌悪、恐怖など、様々な感情があります。
まず、この模範解答から、気づかされることがあります。
感情の抑制ができない→何かに気づいたということ
感情の抑制ができないことについて、表側からではなく、裏側から考えてみましょう。
内部リンク:【思考力を鍛える4つの型】AIに負けない思考方法、思考の型
天気の変化、周囲の見えない空気の変化、相手の行動、相手の言葉の真意。
意識的か無意識的かは人によりますが、何かを察知し、自分の中の感情が変化したからこそ、「感情の抑制ができない」「感情の起伏が激しい」という形で顕在化する訳です。
感情の抑制ができない→感受性が高いということ
ということは、「感情の抑制ができない」「感情の起伏が激しい」という人は感受性が高い人だということです。
何かを感じ取らなければ、感情は変化しません。
これは非常に素晴らしい才能です。
なぜなら、仕事や人生の本質の一つは何かを感じ取り、言語化し、対策を考えることだからです。
言語化するスキルや対策を考えるスキルはアポステリオリ(後天的)な努力でも身に着けることができます。
しかし、感受性や感じ取る力というのはアプリオリ(先天的)に生まれ持った要素が比較的大きいです。
後術しますが、この神様から授かった才能を受容し、どのように生かしていくかが非常に大切なのです。
ロボットやAIに取られる仕事の一つ→感情の要素が無い仕事
更に近年、第4次産業革命の進展もあり、AI、自動ロボット、協業ロボットなどの進歩が著しいです。
テクノロジーの進化により、人間からAI、自動ロボット、協業ロボットに置き換えられる職業も出てきています。
ありふれた模範解答を導き出すのに、感情は不要です。(AI)
決められた手順通りに物を運ぶのに、感情は不要です。(ロボット)
このように人間の感情の介在を必要としない職業はAIやロボットに代替され、どんどんと自動化が進んでいます。
感情が介在する仕事、感情を表現する仕事はAIやロボットに奪われない
高級時計店、高級レストランなどの接客係(→感情によるストーリーの共有)
きめ細かい介護サービス(→感情により共感したり、寄り添う)
アーティスト、作家(→感情の表現)
などなど。
内部リンク:経済産業省HP 第4次産業革命 資料 P13参照
頭の良いあなたはもうお分かりでしょう。
これからの時代を生き残るのは、感じ取り、気づき、表現する力を持った人です。
あなたはこれからの時代を生き残る筆頭でしょう。
感情の抑制ができない人が意識すべきこと→言語化
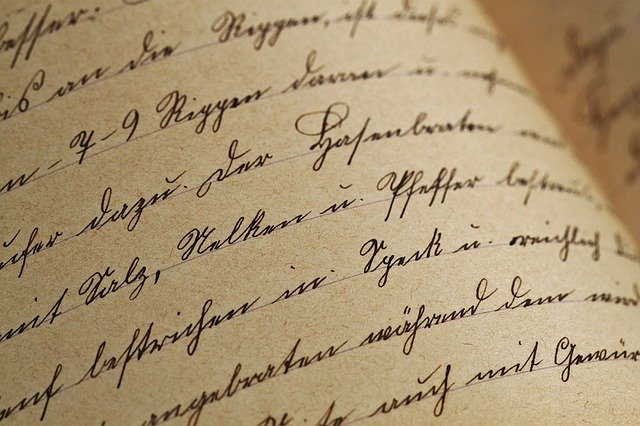
「感情を抑制できないこと」「感情の起伏が激しいこと」「感情の制御が上手くできないこと」これらは全て才能だと思っているというお話は上述しました。
これらの才能を備えた人が身につけたいスキルがあります。
それが言語化です。
感情を言語化すると価値が生まれる
これは世の中を見渡してみると非常に分かりやすいです。
愛や恋愛、ドロドロした感情などを言語化し、作詞作曲すると歌になります。(→アーティスト)
受けたサービスに不満の感情が爆発した時に、何がダメでどうすれば良かったのかを言語化するとマニュアルになります。(→接客業のマネージャー、コンサルなど)
言語化ではありませんが、「感情の起伏が激しいこと」「感情の制御が上手くできないこと」を、絵画やピアノ、ヴァイオリンなどで表現しても良いでしょう。
このように感情を何らかの形で言語化すると、それがそのまま価値になるのです。
感情を言語化すると自分を見失わない
「感情を抑制できないこと」「感情の起伏が激しいこと」「感情の制御が上手くできないこと」これらは才能であると同時に諸刃の剣です。
例えば、暴力的な行為、猥褻な行為、更にそれより酷い段階に進む可能性もあります。
なぜそうなるかと言えば、感情→動物的な本能に直接結びついて、衝動的な行動になるからです。
現代社会ではこれらは許されないことです。
それを防止してくれるのが、言語化です。
感情を理性的に整理整頓するのが言語化です。
言語化すると、自分の感情を客観視でき、落ち着きます。
また上述のように、何らかの価値を生みます。
言語化は才能のあるあなたが、自分を見失わないために、必ず身につけなければならない必須スキルなのです。
感情を言語化する訓練 3選

さて、ここまで読んでくださったあなたには、私が実践してきた言語化のコツを5つご紹介することにします。
感情を言語化する訓練1:語彙力を磨く
感情を言語化する訓練1つ目は語彙力を磨くことです。
要は比喩力が上がるということです。(今の感情にぴったりな例え言葉を探して引き出せる状態になるということです。)
積極的に本を読んで、語彙力を身につけると、感情を言語化しやすくなるのです。
また、語彙を豊富に持っているほど、教養のある人だと思われ、チャンスの幅が広がります。
このようにいいことづくめなのが、本を読み、語彙力を磨くということです。
語彙力が身につくおすすめの本は以下の記事にてご紹介していますので、興味のある方はご一読下さい。
内部リンク:【隠れた名著】おすすめの名著リスト 教養が身につく14冊
内部リンク:【本の楽しみ方】人生を変えるおすすめの本の楽しみ方 5選
内部リンク:【読書ができない、苦手な人へ】人生を豊かにする本の読み方のコツ
内部リンク:【教養とは何か?】教養を身につけるために心掛けたいこと
感情を言語化する訓練2:一人旅に出る
感情を言語化する訓練2つ目は一人旅に出ることです。
語彙力を磨くのと同じくらい効果的なのが、一人旅に出ることです。
一人旅に出ると、様々な景色をインプットしたり、自分自身と向き合い、いつもとは違う感じ取り方をすることができます。
様々な場所で様々な感じ取り方をすると、語彙力と組み合わさり、必然的に比喩力が上がります。
科学的根拠は何もありませんが(笑)、個人的には旅先での読書は本当に自分に染み込み、一生ものの武器になってくれると確信しています。
一人旅にはその他にも様々なメリットがあるので、是非旅に出てみて下さい。
内部リンク:仕事で初めて海外出張へ行く人へ:海外出張前の準備、仕事の進め方
感情を言語化する訓練3:アウトプットを習慣化する
感情を言語化する訓練3つ目はアウトプットを習慣化することです。
「感情を言語化するコツ1:語彙力を磨く」「感情を言語化するコツ2:一人旅に出る」などは感情を言語化するためのインプット部分です。
私はブログが好きですが、ツイッター、note、YouTubeなど、なんでも構いません。
インプット〜アウトプットを繰り返すと、上手く感情の言語化ができるようになり、感情をコントロールしやすくなります。
私の場合は、ブログ、Twitter、読書ノートをメインに毎日アウトプットしています。
是非、何らかのアウトプットを習慣にしてみて下さい。
内部リンク:【ブログのメリット 8選】個人におすすめの自己研鑽→ブログ
最後に、感情的になってしまうことは限度を越えなければ、悪いことではありません。
そのエネルギーをどこに向け、どのような土俵で発散するかを考えることが大切です。
あなたのご健闘をお祈りしています。
今回は以上です。
