こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- 挨拶をする意味、大切さを学びたい人
- 自分が挨拶をできない、苦手だと悩んでいる人
- 会社、職場、近所に挨拶をしない人がいるという人
※この記事と併せて読みたい記事
内部リンク:質問の仕方が上手な人は伸びる:質問力・スキルを伸ばす考え方
内部リンク:【接客が上手い人・下手な人 特徴5選】接客で大切なこと
それでは「ヨット講座」始めましょう。
※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/2/6現在です。)

挨拶とは?挨拶をする意味

我々の日常に当たり前のように根付いている「挨拶」という概念。
「挨拶とは何か?、挨拶をする意味」などについて深く考える機会は意外にありません。
今日は少しそんな観点から本質的に考えてみましょう。
面白いことに気付かされます。
挨拶とは?→仏教語の一挨一拶が起源
まず、挨拶とは何かを考察してみましょう。
挨拶は仏教語の一挨一拶(いちあいいっさつ)が起源です。
(「挨」は軽く、「拶」は強くふれる意) 禅家で、師と修行者、または、修行者同士が出会ったときに、ことばや動作で互いに相手の悟りの深浅などをためすこと。〔碧巖録‐二三則・垂示〕
精選版 日本国語大辞典より引用
ここに深いヒントが詰まっています。
一挨一拶も現代社会の挨拶も本質は変わりません。
挨拶をする意味→お互いのレベルを図るため
挨拶をする意味とは何でしょうか?
よくお聞きする答えが「コミュニケーション」「礼儀」「マナー」「人間関係の構築」などでしょうか。
もちろんこれらもその通りです。
これは後術しますが、挨拶にはその人の本質が全て現れます。
能動性、場の空気を読む力、敬虔さ、教養など。
仕事にも、人生にも直結する能力の要素がたった数秒の挨拶に全て顕在化します。
綺麗事を抜きにすると、職場、レストラン、百貨店、ホテルなど、様々な場所であなたの挨拶でレベルが判断されているのです。
これは100%間違いない事実ですので、知っておきましょう。
もう少しストレートな表現をすると、挨拶をする意味は自分の値打ちを下げないためです。
素敵な挨拶をする人には素敵な挨拶をする人が集まってきます。
挨拶をしない人には挨拶をしない人が集まってきます。
これが自然の摂理です。
挨拶の大切さ→挨拶の質は能力に直結する

鋭いあなたはすでにお気づきかもしれませんが、ここからは「挨拶の大切さ」について考えていきたいと思います。
私の数々の一次情報から断言出来ることがあります。
それは「挨拶=能力の集大成」という事実です。
事例を引き合いに出しながら考えていきましょう。
挨拶の大切さ ポイント1:挨拶の質=能力の集大成
挨拶の大切さ ポイント1つ目は挨拶の質=能力の集大成だということです。
先述しましたが能動性、場の空気を読む力、敬虔さ、教養などです。
能動性→「挨拶を自分からする=様々な事象に対して自分から行動する」
場の空気を読む力→「TPOによる挨拶の声、トーンの使い分け=会議・指示などの声、トーンの使い分け」
敬虔さ→「自分の数秒の命を削って相手に挨拶をすることで敬意を伝える=相手の時間に敬意を払い、期限遵守を徹底する」
内部リンク:【期限遵守・厳守は人生の本質】期限を守れない人が意識すること
教養→「求められている挨拶のレベルという共通言語を理解する=様々な仕事の共通言語を理解する」
このように挨拶の質はそのまま能力の集大成なのです。
「挨拶」を軽く見ない方が賢明です。
挨拶の大切さ ポイント2:挨拶のレベル=企業のレベル
挨拶の大切さ ポイント2つ目は挨拶のレベル=企業のレベルという事実です。
私が新卒入社した会社は東証1部上場の従業員数1万人弱の自動車関連企業です。
世間では大企業とされている会社ですが、意外にも挨拶ができない人が多かったです。
自部署はもちろん、他部署もそのような傾向にありました。
業績は赤字までは行きませんが、比較的利益率が低い会社です。
私が転職した先は某自動車メーカーです。
自動車メーカーに転職した初日に驚いたのは、挨拶のレベルが高かったことです。
仕事のレベルは転職前の会社よりも断然高かったですし、利益率も業界屈指の高さです。
この事実から帰納的に仮説を立てて周囲を観察してみたところ、面白いことに気づかされました。
それが挨拶のレベル=企業のレベルという事実です。
質の高い仕事をする会社の営業マンはきちんと挨拶ができる人でした。
中小企業のオーナー社長がきちんと挨拶をできる人だと、部下の方もきちんと挨拶ができる人でした。そして仕事の質も高いです。
逆も然りです。
質の低い仕事をする会社の営業マンはきちんとした挨拶ができない人でした。
中小企業のオーナー社長が挨拶のできない人だと、部下の方も挨拶のできない人でした。そして仕事の質も低いです。
以上は100%一次情報のノンフィクションです。
企業のレベルは挨拶のレベルに比例するのです。
嘘だと思ったら周囲を観察してみて下さい。
5人以上を確認した平均値は例外なくそのようになります。
挨拶の大切さ ポイント3:挨拶の質で付き合える人が変わる
挨拶の大切さ ポイント3つ目は挨拶の質で付き合える人が変わるという事実です。
これは教養と非常に似ています。
内部リンク:【教養とは何か?】教養を身につけるために心掛けたいこと
何を標準言語にし、誰との「共通言語」を話すかで付き合える人が変わり、人生が変わります。
具体的に考えてみましょう。
Aさんはギャンブル・お酒・噂話が趣味です。
Bさんは読書・哲学・一人旅が趣味です。
AさんとBさんで話が噛み合うでしょうか?
絶対に話は噛み合いません。
これは挨拶も全く同じ話です。
Aさんは自分から挨拶をしません。挨拶をされても目を合わさず、聞こえないレベルに小さな声で挨拶をします。
Bさんは常に自分から挨拶をします。極力目を合わせて挨拶し、TPOに合わせて声のボリュームを変えます。
Aさんの周囲には同じく挨拶をしない人が寄ってきます。
Bさんの周囲には同じく挨拶をする人が寄ってきます。
その後、どうなるかはあなたのご想像にお任せします。
どちらになるかはあなたの自由ですが、個人的にはBさんを目指したいと思います。
挨拶の大切さは世界でも同じ
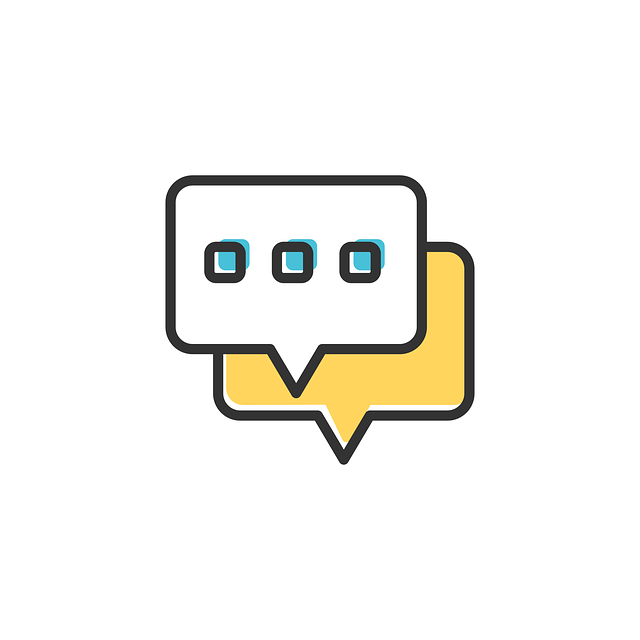
グローバル化が日に日に進む現代社会。
様々なシーンで外国の方と接する機会が多いのではないでしょうか?
内部リンク:仕事で初めて海外出張へ行く人へ:海外出張前の準備、仕事の進め方
コロナ禍の現在では少し事情は異なると思いますが、目を合わせて挨拶をするのは当然として、全員と一人一人握手をしていくことは普通です。
また私が滞在したトルコなどでは、ハグをして、頬と頬を合わせる挨拶も普通に行われています。
「郷に入れば郷に従え」ということで、私も190cmオーバーの大男とたくさんハグをしました。(笑)
恥ずかしがらずにこのような挨拶をしたからこそ、本気で打ち解けられたと確信しています。
仕事の面でも、当時20代の私の指示に30代/40代のローカルスタッフが素直に従ってくれたのは、「挨拶で打ち解けたから」だと確信しています。(もちろんそれ以外の工夫もしました。)
デジタル化、グローバル化でも真に大切な本質というのは意外にアナログな部分にあるのではないでしょうか?
最後に一つだけ言わせて下さい。
「挨拶」に拘ると人生が変わります。
今回は以上です。
