こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- 本の目利きのコツを知りたい人
- 濃い読書をするための本の選び方のコツを知りたい人
- ビジネス書、哲学書、小説などの本の選び方のコツを知りたい人
※この記事と併せて読みたい記事
内部リンク:【隠れた名著】おすすめの名著リスト 教養が身につく14冊
内部リンク:効果大:読書ノートの書き方はここで差がつく!人生の相棒の作り方
内部リンク:【本の楽しみ方】人生を変えるおすすめの本の楽しみ方 5選
内部リンク:【小説の楽しみ方】人生を変える小説の楽しみ方 5選
内部リンク:【読みにくい本/難解な本の読み方】読みやすくする工夫 4選
それでは「ヨット講座」始めましょう。
※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/1/11現在です。)

本の目利き力・選び方の重要性
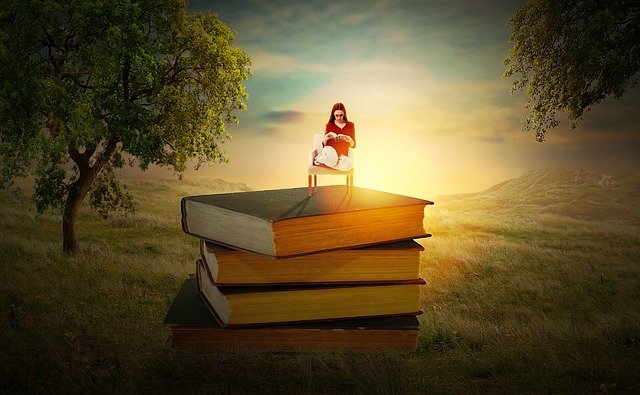
はじめに、本の目利き力・選び方の重要性について考えていきましょう。
それにはいくつかの理由があります。
本の目利き力・選び方が重要な理由1:自分の人生が変わる
本の目利き力・選び方が重要な理由1つ目は自分の人生が変わるということです。
「そんな大袈裟な・・・」と思われた方もいらっしゃるかと思います。
しかし、様々な一次情報を確認してきた私から申し上げさせて頂くと、100%の確度に近い事実です。
極論ですが、「誰が書いた本を読むか」「どんな本を読むか」で人生は変わります。
本というのは人生の軌跡・思考・思想・語彙のエッセンスが全て詰まった「人類最大の発明」と言っても過言では無いツールです。
どんな質の「人生の軌跡・思考・思想・語彙」を自分の中にインストールするかによって、人生は変わるに決まっています。
なぜなら、仕事、人生、恋愛などで何らかのアウトプットをする質は、そのままインプットの質によって左右されるからです。
これには一才の例外はありません。
本の目利き力・選び方が重要な理由2:相対的に寿命が長くなる
本の目利き力・選び方が重要な理由2つ目は相対的に寿命が長くなることです。
人生というのは有限です。
人はいつかは必ず死にます。
人生の中では、悩みの解決、仕事での問題を解決、余暇の充実などを目的とし、様々な本を読むでしょう。
イマイチな本を20冊読むよりも、質の高い本質が記載された本を1冊読む方が確実に自分の人生に対して好影響を与えます。
20冊読んでもあまり効果が無い本は、自分の時間資産を流出させている状態です。
1冊読んで本質を得ていれば、時間資産の流出を最小限に抑えられます。
私は意外に遠回りに価値があると思っているタチなので、何やら逆説的ですが。(笑)
本の目利き力・選び方で人生の有効寿命は変わるのです。
この記事を読んでいる真面目で優秀なあなたは、この2点で本の目利き力・選び方の重要性をお分かり頂けたと思います。
内部リンク:【時間感覚を制するものは人生を制す】時間感覚を鍛える5つの方法
本のアタリ・ハズレの定義
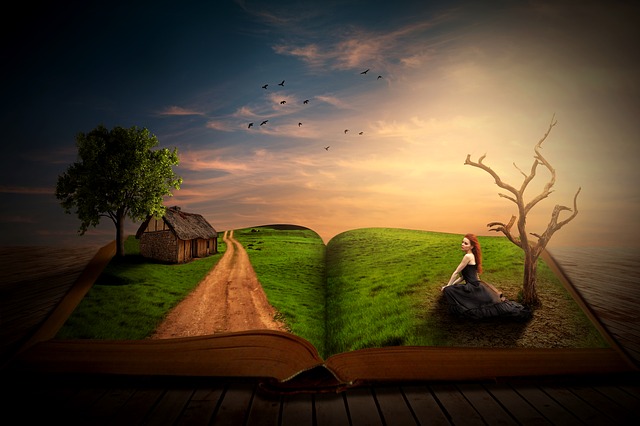
本の目利き・選び方のコツのご説明に入っていく前に、私が考えるアタリ本・ハズレ本の定義について言及しておきます。
これは様々な方がそれぞれの正解を持っているかと思いますが、今回は私が考える内容をご紹介します。
アタリ本の定義1→「ハッ」とさせられる考え方やフレーズが1つでもある
アタリ本の定義1つ目は「ハッ」とさせられる考え方やフレーズが1つでもあることです。
本というのは、大体2,000円前後、高いものでも1万円弱です。
本の随所に「ハッ」とさせられる考え方やフレーズがあるのならば、それは究極のアタリ本です。
ハズレ本の定義1→「ハッ」とさせられる考え方やフレーズが1つも無い
逆にハズレ本の定義1つ目は「ハッ」とさせられる考え方やフレーズが1つも無いことです。
自分の教養レベルが追いついていないのか、単純につまらないのかは、客観的な見極めをする前提として、「ハッ」とさせられる考え方やフレーズが1つも無い本を選んでしまった時は「ハズしたな」という気持ちになります。
しかし、転んでもタダでは起きない発想が大切です。
この記事を書いている私のように、「ハズレを引かないコツ」を学べる材料と考えれば、ある意味アタリなのかもしれません。
アタリ本の定義2→2回以上読み返したくなる本
アタリ本の定義2つ目は2回以上読み返したくなる本です。
何かのタイミングで読み返したくなる本というのは究極のアタリ本だと考えています。
本というのは、自分の成長と共に感じ取れるものが変わってきます。
私には何十回も読み返し、その度に気づきを与えてくれる本があります。
そんな本があると「人生が充実しているな」と感じるのは私だけでしょうか。
ハズレ本の定義2→読んだ瞬間処分したくなる本
逆にハズレ本の定義2つ目は読んだ瞬間、処分したくなる本です。
「この本を読み返すことは二度度ないな」と思ったり、「場所を取るから今すぐ処分したい」と感じるような本はハズレ本でしょう。
本の目利き・選び方のコツ 4選
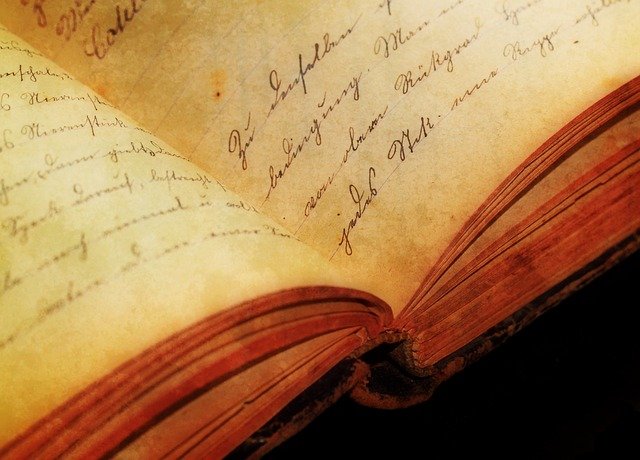
さて、ここからは本の目利き・選び方のコツを4つに分けてご紹介していきます。
あくまで「私がアタリと思う本」を目利きしてきた方法なので、独断と偏見にまみれていることはあらかじめご承知下さい。
しかし、これらのポイントを理解するだけでグッと質の高いアタリ本を目利きできるようになるとの確信を持っています。
本の目利き・選び方のコツ1:著者の学歴をチェック
本の目利き・選び方のコツ1つ目は著者の学歴をチェックすることです。
気になったキーワードや勉強したい分野が出てきた時には、書店に出向きます。
そして本を選んでいきます。
私の場合は、この時に学歴記載があり、高学歴の人が書いた本を優先します。
先述したように本には「人生の軌跡・思考・思想・語彙」が詰まっています。
綺麗事を抜きにすると「思考・思想・語彙」は確実に学歴と比例します。
※高学歴でない著者の方がダメだと言っているのではありません。確率論としてのお話です。
そして、私には複数人贔屓にしている著者がいますが、揃いも揃って高学歴です。
ジャン・ボードリヤール氏は旧パリ第4大学(現ソルボンヌ大学)の出身です。
フランスの大学だと凄さが分かりにくいかもしれませんので、日本人で贔屓の著者を何人か挙げます。
20代向けビジネス系:故 瀧本哲史氏→東京大学 法学部
自己啓発系:千田琢哉氏→東北大学 教育学部
小説:伊坂幸太郎氏→東北大学 法学部
本の目利きの際に複数冊で迷った場合は、高学歴の方の書いた本を優先した選び方をすると、外れる確率が下がります。
本の目利き・選び方のコツ2:著者の職歴をチェック
本の目利き・選び方のコツ2つ目は著者の職歴をチェックすることです。
特にビジネス書を選ぶ際には著者の職歴が大手企業出身である本の質が高い傾向にあります。(大手企業=日経225銘柄の企業、またはそれに準ずる知名度の企業)
大手企業や有名外資企業というのは、徹底的に仕組み化することを考えます。
仕組み化とは誰がやっても、同じ成果や品質を再現できる仕組みを考えることです。
また、大手企業、有名外資企業社内には偉大な先人達や入社するハードルを突破した優秀な人材の知恵が溢れています。
そのような環境に日常的に身を置いている方が人が本を書けば、必然的に質が高くなる可能性が高まります。
そんな観点で本を目利き・選んでみると様々なことに気づかされます。
参考ですが、学歴で先述した方々の職歴です。
哲学書:ジャン・ボードリヤール氏→旧パリ第4大学(現ソルボンヌ大学)→パリ大学ナンテール校助手→パリ大学ナンテール校教授(社会学)
20代向けビジネス系:故 瀧本哲史氏→東京大学 法学部→東京大学大学院 助手→マッキンゼー→独立(エンジェル投資家、京都大学客員准教授等)
自己啓発系:千田琢哉氏→東北大学 教育学部→日動火災海上保険株式会社(現、東京海上日動火災保険株式会社)→株式会社船井総合研究所→独立
本の目利き・選び方のコツ3:本の帯のフレーズを見る
本の目利き・選び方のコツ3つ目は本の帯のフレーズを見ることです。
本の帯のフレーズというのは本の中身から抜き出した出汁の一滴です。
いくつか本の帯から引用しましょう。
新しいゲームのはじまり、ルールは不確実性
あらゆる領域に不確実性が侵入し、安心できる世界が終わりを告げるという状況は、不確実性自体がゲームの規則になりさえすれば、すこしも否定的な宿命ではない
ジャン・ボードリヤール氏「不可能な交換」紀伊國屋書店 本の帯より引用
「テロリズムはスーパー・パワーとなった権力の内側で起こっている解体の過程の暴力的な表現にすぎません。だからこそ、9.11のような、たった一度の重大なテロ行為によってテロリズムの感染が起こるだけで、あの支配的文化の中心部にテロルのあらゆる兆候を解き放つにはじゅうぶんなのです」
ジャン・ボードリヤール氏「暴力とグローバリゼーション」NTT出版 本の帯より引用
これは私がもっと読みたいと思ったフレーズなので、あなたに響くかは分かりません。
本の帯を見て、「読んでみたい」と思えるフレーズがある本は、ハズレが少ないです。
逆に本の帯を見て、しっくりこなかった本を選ぶと大体「失敗した」という気持ちになります。(笑)
もちろん外すこともありますが、この二つの組み合わせで、外す確率は8%以下まで減少しました。
本の帯で目利きすると、意外に外さないのです。
一度書店で意識して見てみて下さい。
本の目利き・選び方のコツ4:贔屓の著者が引用している本を選ぶ
本の目利き・選び方のコツ4つ目は贔屓の著者が引用している本を選ぶことです。
本の目利き・選び方のコツ1、2、3を実行して、贔屓の著者を発見したら非常に有効な方法がこちらになります。
これは私自身の外れ確率が1%以下にまで減少した最も近道な方法です。
大体の場合、贔屓の著者の本の中で、著者が引用している個人名、引用している本の一節があります。(小説は少ないかもです。)
これらの個人や引用されている本を購入すると極めて外す確率が低くなります。
贔屓の著者が見つかったら、是非試してみてください。
今回は以上です。
