こんにちは、ヨットです。
この記事は以下の人に向けて書きました。
- 読みにくい本/難解な本に挑戦したいと考えている人
- 読みにくい本/難解な本の読み方を学びたい人
- 読みにくく挫折した本に再度チャレンジしたい人
※この記事と併せて読みたい記事
内部リンク:【隠れた名著】おすすめの名著リスト 教養が身につく14冊
内部リンク:効果大:読書ノートの書き方はここで差がつく!人生の相棒の作り方
内部リンク:【本の目利き・選び方のコツ】アタリ確率を上げるには○○を確認
内部リンク:【読書ができない、苦手な人へ】人生を豊かにする本の読み方のコツ
内部リンク:【本の楽しみ方】人生を変えるおすすめの本の楽しみ方 5選
内部リンク:【小説の楽しみ方】人生を変える小説の楽しみ方 5選
それでは「ヨット講座」始めましょう。
※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/1/9現在です。)

読みにくい本/難解な本の正体
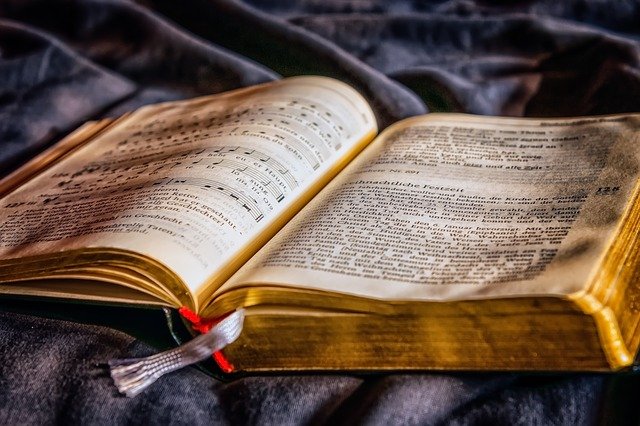
この記事を読んでくださっている人は「読みにくい、難解だ」と感じる本に出会ったことがある人がほとんどでしょう。
私にも「読みにくい、難解だ」と感じる本が何十冊もあります。
まずは読みにくい本/難解な本の正体を紐解いていきましょう。
読みにくい本/難解な本の正体1:著者の視点とのズレ
読みにくい本/難解な本の正体1つ目は著者の視点とのズレです。
人間同士の会話でもそうですが、片方が日本語、片方が英語だと当然会話は成立しませんよね。
これは本でも同じです。
特に哲学者の本を読む場合などがこれに該当します。
著名な哲学者のほとんどは天才中の天才です。
視野の広さが尋常ではなく広く、見ている視点、着眼点が鋭いです。
その視点についていけないほど、「この本は読みにくい、難解だ」と感じる訳です。
後術しますが、この著者との視点のズレを埋める工夫をすることが、読みにくい本、難解な本を読破するコツです。
読みにくい本/難解な本の正体2:語彙力のレベルの高さ
読みにくい本/難解な本の正体2つ目は語彙力のレベルの高さです。
読みにくい本/難解な本には高い教養レベルを求められる本も少なくありません。
横文字でパッと思いつく内容であれば、シュミラークル、カタストロフ、アイロニー、ヘゲモニー、アポトーシス、シニフィアン/シニフィエ、ヒエログリフ、ディアスポラ、ルサンチマン、パトス、ロゴス、エトスなどでしょうか。
日本語ならば、補綴(ほてつ)、奢侈(しゃし)、蕩尽(とうじん)、呻吟(しんぎん)、零落(れいらく)、卑賤(ひせん)、曙光(しょこう)、諧謔(かいぎゃく)、奸計(かんけい)、紊乱(びんらん)、貪婪(どんらん)、慇懃(いんぎん)、頽廃(たいはい)、跋扈(ばっこ)、晦渋(かいじゅう)、怯懦(きょうだ)、籠絡(ろうらく)、瀰漫(びまん)などでしょうか。
これらの意味がパッと分かったあなたはかなりの教養レベルの持ち主でしょう。
更には「現実原則」といったありきたりの日本語に見えるものでも、精神分析学の用語であったりします。
自分が意味の分からない日本語は英語、その他言語の本を読んでいるのと同じですからね。
かつて、四苦八苦しながら読んでいた自分を思い出します。(笑)
読みにくい本/難解な本を読みやすくする方法 4選
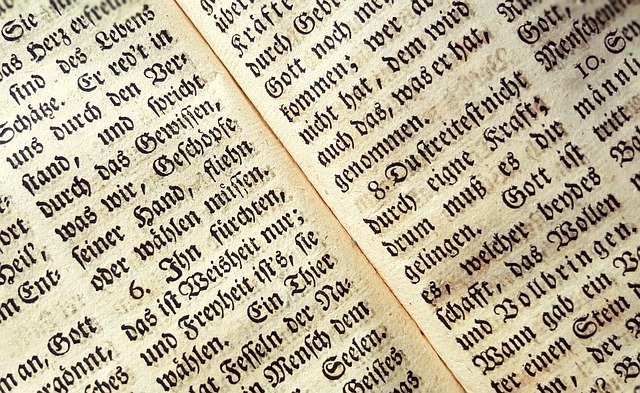
さて、ここからは読みにくい本/難解な本を読みやすくする方法を4つに分けて解説していきます。
ありきたりな方法から少しユニークな方法まで、ご紹介していきます。
あなたの肌感覚に合ったものがあれば、お試し下さい。
読みにくい本/難解な本を読みやすくする方法1:翻訳者解説から読む
読みにくい本/難解な本を読みやすくする方法1つ目は翻訳者解説から読むことです。
哲学書などで著者が外国人の場合は翻訳者がいます。
そのような大抵の本には最後に翻訳者の解説がついています。
まずは最後の翻訳者の解説から読みましょう。
翻訳者の解説から読むメリットは「本の全体像、著者の主張内容、キーポイント」を把握できることです。
宝探しの地図をざっと見た上で、実際に探検するイメージと同じです。
「読み進める→分かりにくい、難解な部分→翻訳者解説を再度読みながら理解に勤める→読み進める」
このように翻訳者の解説を道標にしながら読むと、読みにくい本や難解な本も意外に読破できてしまいます。
一度試してみて下さい。
PS.東京大学を卒業した頭脳明晰な翻訳者でさえも、「読みにくい、難解な本で翻訳が大変だった」と告白している本もあったりします。そんな告白を翻訳者解説で読んで、「自分だけではなくて良かった」とほっとできるのもメリットかもしれません。(笑)
読みにくい本/難解な本を読みやすくする方法2:解説書から読む
読みにくい本/難解な本を読みやすくする方法2つ目は解説書から読むことです。
私は哲学書などの原書にいきなり挑んで、ボコボコにされながら、徐々に理解したタチです。
しかし、効率よく理解するという意味ではイマイチな方法でした。(笑)
ジェレミー・ベンサムを理解したければ、日本人の著者の解説書から読むのが良いでしょう。
フリードリヒ・ニーチェを理解したければ、日本人の著者の解説書から読むのが良いでしょう。
今は漫画の解説書もある時代です。
読みにくい本/難解な本を読みやすくする方法1つ目の翻訳者解説から読むのは非常に効果的ですが、比較的短いページ数で概略だけ解説されているので、多少の物足りなさは残ります。
解説書は1冊丸々が解説に費やされている訳です。
当然、解説を目的としていますから、比較的分かりやすいです。
原書と解説書を行ったり来たりしながら読むと、読みにくい本、難解な本を読破しやすいです。
少し小難しそうな本を購入するときは、解説書もセットで購入してみてはいかがでしょうか。
理解度が深まります。
読みにくい本/難解な本を読みやすくする方法3:視点の抽象度・角度を合わせる
読みにくい本/難解な本を読みやすくする方法3つ目は視点の抽象度・角度を合わせることです。
例えば、著者が世界について語っているのに、自分が日本について考えていたら話は噛み合いません。
または著者が具体的な行動について語っているのに、自分は理想論について考えていたら話は噛み合いません。
ポストモダン的な思想の持ち主なのか?、徹底的な資本主義的な思想の持ち主なのか?、などを観察しながら、同じ抽象度、同じ角度に目線を合わせて本を読むことが大切です。
いきなりピタリとチューニングするのは難しいですが、この意識を継続的に持つと、徐々に抽象度、角度を読み取る力が鋭くなり、読みにくい本、難解な本の概略や主張を素早く理解できるようになります。
徐々に意識してみましょう。
※参考になりそうな関連記事は以下です。
内部リンク:【視野を広げると生き方の可能性が広がる】視野が広い人の考え方
読みにくい本/難解な本を読みやすくする方法4:理解不能な本を読み切る
読みにくい本/難解な本を読みやすくする方法4つ目は理解不能な本を読み切ることです。
少し逆説的なのですが、今の自分のレベルでは理解不能な本を分からなくてもいいので最初から最後まで読み切ってみて下さい。
「何故そうなのかを論理的に説明せよ」と言われても説明できないですが(笑)。
私の場合はそのような本が何冊かあり、そのうちの一冊がピエール・クロソウスキーの「生きた貨幣」です。
この本を読んでから、他の本を読むと、異常にスラスラ読めます。
理解不能な本を上手く活用することにより、読みにくい本/難解な本を読みやすい本に変えていく。
そんな逆説的な方法もあることは頭の片隅に置いておいて下さい。
読みにくい本/難解な本を人生の盟友にする
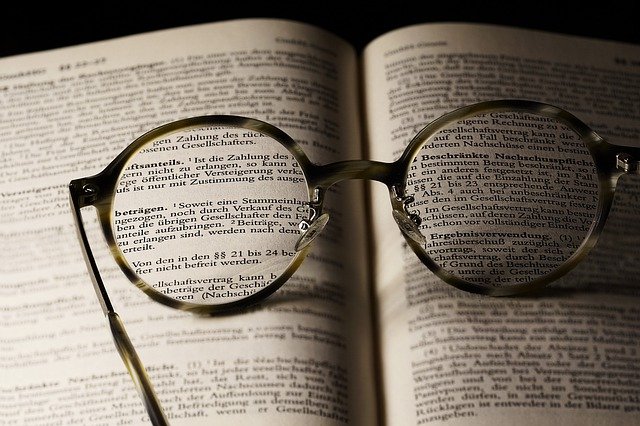
最後に読みにくい本/難解な本に挑んでいる、もしくは挑もうとしている真面目で優秀なあなたにメッセージです。
噛めば噛むほど味がじわじわ出てきます。
自分の成長と共に噛む力が成長し、今まで以上に良い味や思わぬ発見を提供してくれます。
シンプルで分かりやすい本ももちろん素晴らしいですが、読みにくい本/難解な本と一緒に長い人生を歩んでゆく。
そんな本の楽しみ方もあるのではないでしょうか。
すぐに分からないものの方が人生にとって真に必要なものであると私は考えています。
今回は以上です。
